
毎月、猿が仲間に「ここにバナナがあるぞー」と知らせるみたいな感じに、英語で書かれた本について書きます。新刊には限定せず、とにかくまだ翻訳のない、面白い本を紹介できればと。
まず、すでに邦訳のある作品から話を始めることをご容赦いただきたい。
アメリカの黒人作家ラルフ・エリスンの短篇「広場でのパーティ」を初めて読んだときの衝撃は忘れがたい。1994年にエリスンが歿したあとに発見された、“Early Stories”と書かれたフォルダに入っていた、おそらくは1940年前後に書かれ、タイトルもついていなかったタイプ原稿が1996年に出版されたのである(“A Party Down at the Square”というタイトルは発見した編集者がつけた)。
一人の少年の目を通して、町の広場で黒人が焼き殺されるさまが語られる。火がだんだん迫ってきて苦しそうに悶える黒人、それを囲んではやし立てる町の人々。折しも天候は嵐、それがどんどんひどくなって、そこへエンジンが故障した飛行機が落下してきて、広場はすさまじい混乱に陥る。
そのさなかにも、焼き殺されている黒人はますます苦しそうな様子になって、いっそ殺してほしいと乞いはじめる。“Will somebody please cut my throat like a Christian?”(どなたかあたしの喉を、キリスト教徒らしく切ってくれませんかね?)。だが首謀者の一人が答えて言う。“Sorry, but ain’t no Christians around tonight. Ain’t no Jew-boys neither. We’re just one hundred percent Americans.”(悪いな、今夜はキリスト教徒は一人もいないんだ。ユダ公もいないし。俺たちみんな、100パーセントアメリカ人なんだよ)。
こうした展開をエリソンは、ふだんは中西部のオハイオ州に住んでいて、いまはたまたま南部の親戚のところへ遊びに来ている少年の目を通して描いた。つまりこの少年、南部的な黒人差別に染まってはいないが、さりとて差別は悪だというような思いにもまだ目覚めていない。まったく白紙の目で、リンチを一種のお祭りごととして(まさに「パーティ」として)眺めている。その言葉は鈍感そのものだが、体は残酷な事態に敏感に反応している。この対比が実に効果的なのである。
もちろん効果的であればこそ、1940年前後に、この作品を駆け出しの黒人作家が(エリスンは1914年生まれ)発表できる可能性など皆無だっただろう。作者の死後に原稿が発見されて陽の目を見ただけでも喜ばないといけない。エリスンといえば、『見えない人間』(The Invisible Man, 1952)で黒人文学を大きく前進させた作家だが(その後40年あまり、ついに第二長篇を完成させることができなかったが、この一作だけで文学史における地位は保証された)、個人的には、この「広場でのパーティ」も短篇ならではの衝撃度と密度において等しく重要だと思う。
ちなみにこの作品の邦訳は『ラルフ・エリスン短編集』(松本一裕・山嵜文男訳、南雲堂フェニックス)に収められている。また、『Monkey Business』Vol. 2(ヴィレッジブックス、2008)には拙訳を掲載しました。
✴︎
最近、朗読会や講演で翻訳作品を朗読していて一番反応がいいのは、圧倒的にゾラ・ニール・ハーストンの「ハーレムの書」(Zora Neale Hurston, “The Book of Harlem”)である。
南部からニューヨークに移り住んだ黒人の男の物語を、欽定訳聖書(King James Bibleと呼ばれる、1611年刊の、聖書の文体と言えばまずこの版のことを指す権威ある英語版聖書)にハーレム風のスラングを混ぜて語る。とにかくムチャクチャ可笑しい。
5. Then spake he to his father thus: “lo, I am become a man. Shall I not go forth and seek my fortune, and perchance find a maiden of exceeding virtue that I may take her to wife?”
6. “Perhaps,” saith his father, “but wherefore goeth thou to a far city to seek a wife among Jezebels, when there be Cora, thy neighbor’s daughter, a damsel of great piety, who wilt bear thee many sons, and moreover, she is a mighty biscuit cooker before the Lord.”
7. Then did Jazzbo stand before his father and snort with scorn, saying, “Wherefore must I wed a cooker of biscuits when I crave not bread? Behold, man was not made to live by bread alone, but upon every thrill that proceedth from life. Go to, now, wherefore should I marry that drink of boiled water, when in great Babylon there are females that are as a cocktail to the tonsils.”
5 然ばジャズボ、父に言へり、「見よ、我、男になれり。ならば我、世に出て富の道を求むべきにあらずや、それでついでにさ、大いに徳高き乙女を見出し、妻に娶るべきあらずや」
6 「まあそうかもしれんけど」と父言へり、「然ど汝、何故に遠くの都市へ行きて邪なる毒婦の中に妻を探すや、お隣のお嬢さんのコーラちやん、信心篤き少女子にして、必ずや汝に多くの息子を産まん、それにあの子の焼く丸麺麭は天下一品だぜ」
7 然してジャズボ、父の前に立ち、軽蔑に鼻を鳴して言へり、「我の焦れしもの麺麭には非ず、ならば何故我、丸麺麭焼きを娶るべきか。見よ、人は麺麭のみにて生くるに非ず、生より出る諸の快楽を味はふが為なれば。勘弁してくれよ、我なんぞあんなただのお湯湧したみたいのを娶るべけんや、大いなるバビロンに行きたればこりやもう扁桃腺に入つてくるカクテルみたいないい女がわんさといるつてのにさ」
「ハーレムの書」は1927年に、黒人系の週刊新聞The Pittsburgh Courierに掲載された(なので、「広場でのパーティ」のようにまったく世に出なかったわけではない)が、単行本に収録されたのは、つい去年、2020年に刊行された短篇集Hitting a Straight Lick with a Crooked Stick(『曲がった棒でまっすぐぶっ叩く』)においてである。2018年には、ハーストンの文化人類学者としての仕事を収めたBarracoon(『奴隷収容バラック』)も刊行されている(こちらは初めて世に出た)。
ハーストンが亡くなったのは1960年であり、いまだこのように未発表・未収録の作品が刊行されているのは驚きだが、そもそも(以下は、アメリカ文学史の常識の単なるおさらいである)ハーストンは1920~40年代に黒人女性としてのハンディキャップと闘いつつ学者・作家として活躍したものの、以後まったく忘れ去られ、最後は福祉ホームに入って無一文で死に、その墓には墓石もなかった。著作もすべて絶版になっていた。
1970年代に入って、当時新進気鋭の女性作家だったアリス・ウォーカーがハーストンを発見し、75年に雑誌『ミズ』に“In Search of Zora Neale Hurston”(ゾラ・ニール・ハーストンを探して)と題した文章を発表して再評価を呼びかけ、これをきっかけに著作が続々再刊され、いまでは代表作Their Eyes Were Watching God(『彼らの目は神を見ていた』、1937)などはアメリカ文学の古典と見なされている。そして2020年刊の『曲がった棒でまっすぐぶっ叩く』からわかるように、その再発見はいまも進行中なのである。
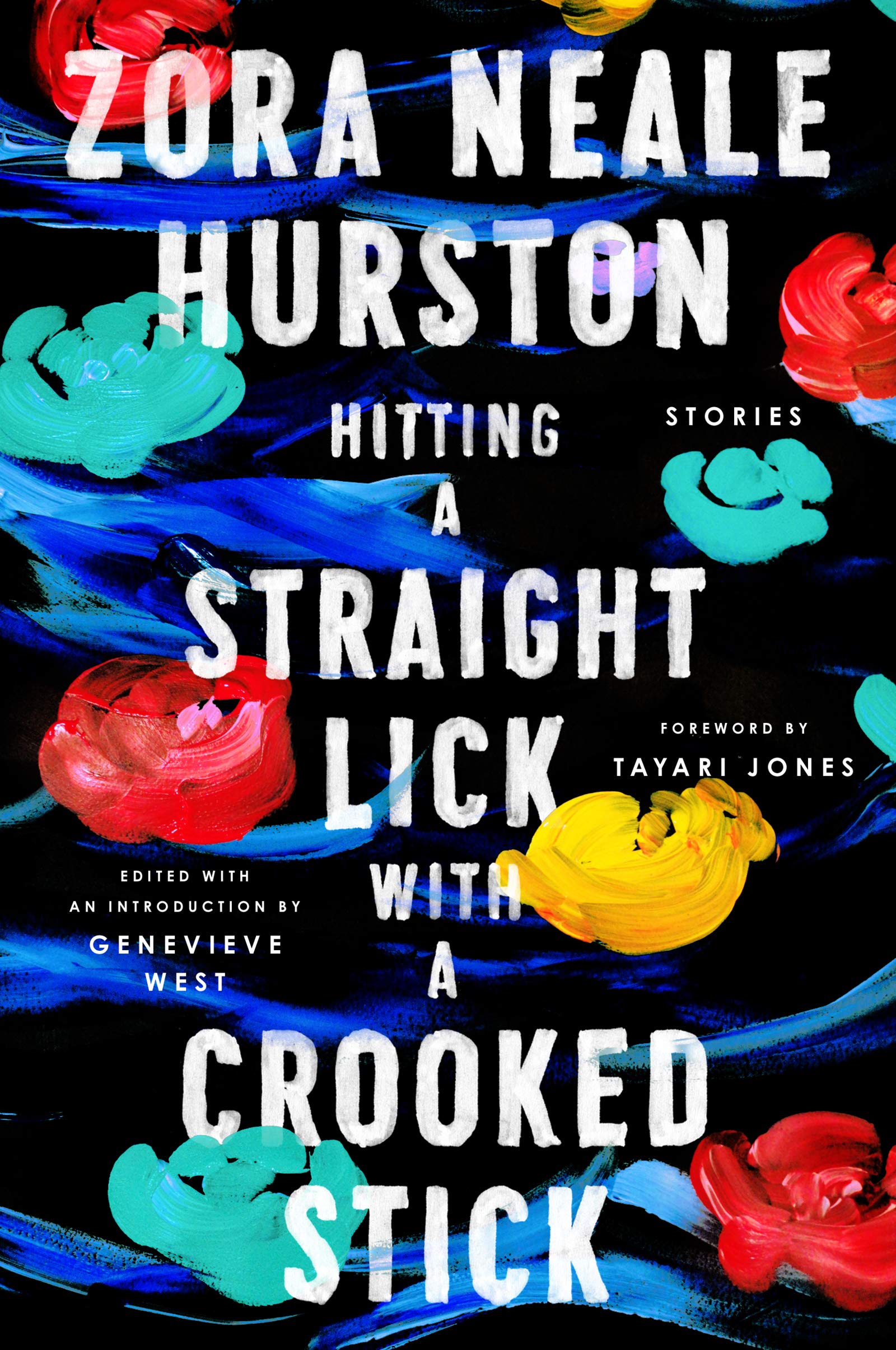
✴︎
というわけで、アメリカの黒人文学に関しては、世に出てしかるべき作品がさまざまな理由で出てこなかったのであり、まだまだ再発見・新発見があるんじゃないかと思っていたら、今年の4月、黒人文学といえば誰もが名を挙げる重要作家リチャード・ライトが1942年に書いた未発表中篇小説が刊行された。タイトルはThe Man Who Lived Underground(『地下で生きた男』)、刊行元はアメリカ文学の古典叢書を何百冊と刊行してきた非営利団体The Library of America。
ただしこれは、まったく未知の作品が突如80年後に発見されて出版された、というのとは少し違う。実のところ、この作品の三分の二は、もうずっと前から世に知られていた。1945年、ライトはこの中篇の最初の三分の一を削除し、残り三分の二にある程度加筆して、同じく“The Man Who Lived Underground”と題した長めの短篇を発表したのである。そしてこの短篇は、ライトが歿した翌年の1961年に刊行された短篇集Eight Menにも収録された(1969年に赤松光雄・田島恒雄訳で晶文社から出た『八人の男』での邦題は「地下にひそむ男」)。
今回は、その削除された三分の一を含む、いわば「完全版」が刊行されたわけである。
問題は、その初めて世に出る三分の一。読めばすぐ、なぜこの部分が1940年代には削除されたかがわかるし、これがあるとないとでは、作品の意味が全然違うこともわかる。
何しろ50ページあまり、ほぼすべて、警察による一人の黒人男性への不当な暴力の描写なのである。ほとんどどのページを引用してもいいようなものだが、たとえば——
Lawson grabbed the collar of his shirt and snatched him forward; again he lay sprawled on the floor. He smelt the acrid odor of a cigar butt. Blows came so hard and fast that the sheer pain of them made him realize that they were beating him with a blackjack. He groaned. The toe of a shoe came like a jabbing hot iron into the nape of his neck; he gave a short, involuntary scream. They jerked him to his feet and pushed him again into the chair. He saw a blob of blood on his shirt.
“Do you want to talk now, boy, or do you want some more?”
His lips moved, but no words came. Johnson placed a hand tenderly upon his shoulder.
“Listen, boy, don’t you want to go and see your wife?”
“Yes, sir,” he managed to whisper.
“Then tell us what you did.”
“I . . . I-I ain’t done n-n-nothing . . .”
A fist exploded between his eyes and he went backwards, toppling with the chair; his head struck the wall, banging twice from the force of the blow.
ローソンが彼のシャツの襟を摑み、ぐいっと前に引っぱった。彼はまたも床にばったり倒れた。葉巻の吸殻のえぐい臭いがした。殴打はあまりに強く、速く、そのすさまじい痛さに、棍棒で殴られていることを彼は悟った。彼はうめき声を漏らした。誰かの靴の爪先が、熱した鉄のようにうなじに突き刺さった。彼は思わず短い悲鳴を上げた。刑事たちは彼の体を摑んで立ち上がらせ、押してふたたび椅子に座らせた。シャツに血のしみが見えた。
「どうだ、これで話したくなったか、それとももっとやってほしいか?」
彼の唇が動いたが、言葉は出てこなかった。ジョンソンが片手を優しく彼の肩に置いた。
「なあおい、お前、女房に会いに行きたくないか?」
「はい、行きたいです」彼はかろうじて小声で言った。
「じゃあ何をやったか話せ」
「な、なにも……や、や、やってません」
目と目のあいだで拳が炸裂し、彼はうしろに倒れ、椅子と一緒にひっくり返った。頭が壁にぶつかり、殴打の勢いで二度ガン、ガンと打った。
一週間の給料を受けとり、妊娠した妻のもとに帰ろうと意気揚々街を歩いていた黒人男性フレッド・ダニエルズは、殺人犯を探している刑事たちに捕らえられ(本当に「こいつにしとこう」という感じで何の根拠もなく捕らえられるのだ)、拷問と言うしかない取り調べを続け、自白書に無理やり署名させられるのである。
まあ当然だろうが、これまで出た書評のほとんどが、ダニエルズが受ける虐待に触れるなかでジョージ・フロイドさんの名を挙げている。80年経っても何も変わっていない、という嘆き。ある意味では、これほどタイムリーな出版もちょっとない、と言えるかもしれない。
ふたたび文学史をおさらいするなら、1940年に刊行されたリチャード・ライトのデビュー作Native Son(邦題『アメリカの息子』)は、殺人犯として処刑される黒人青年ビガー・トマスを人種差別の犠牲者として描き、アメリカ社会を根本から批判して大きな反響を呼び、黒人文学はこの一冊から始まったと言われた(まあいまでは、その三年前に出たゾラ・ニール・ハーストンの『彼らは神を見ていた』を挙げるまでもなく、もっと前からさまざまな黒人文学があったと捉える方が普通だろうが)。
『地下で生きた男』は、ライトが『アメリカの息子』の大成功のあとに次に書いた本である。出版社としては、普通なら一刻も早く第二作を出したいところだろうが、ハーパー&ブラザーズ社はこの本の刊行を(まあ無理もないことだが)拒否した。そしてライトは、拒否された原因となった部分を削除し、短篇として発表したのである。量的には三分の二が残っていたとはいえ、ほとんど別の作品になったと言ってよい。
今回出た完全版では、警察の暴力がえんえん続いたあと、ダニエルズはすきを狙ってダニエルズが警察署から脱走し、マンホールから地下水道に降り立つ(1945年の短篇版はここから始まる)。ダニエルズは地下で生きのびる空間を確保し、さまざまな建物(教会、映画館、宝石店、肉屋、果物屋等々)の内部を壁やドアのすきまから覗き見る。そこでのダニエルズは、ほとんど別人のように思える。逮捕され拷問されたときはあれほど妻と連絡を取りたがったのに、いまでは妻のことも—— そもそも誰のことも—— まったく考えず、地下でただ一人存在することに、ある意味で充足しているようにさえ見えるのだ。たとえば、宝石店の地下に忍び込んだ彼は、金庫から巨額の金を盗むが、それも金を遣うためではなく、ただ単に、自分の自由を確かめるために盗むように思える。こうして彼のふるまいはどんどん奇怪になっていく。
He was free! He remembered how he had hugged the few dollars Mrs. Wooten had given him and he wanted to run from the underground and yell his discovery to the world.
He finally controlled his laughter and swabbed all the dirt walls of the cave with glue and pasted them with green bills; when he finished, he stood in the center of the room and marveled—— the walls blazed with an indescribable yellow-green fire. Yes, this room would be his main hideout; between him and the world that had rejected him would stand this mocking symbol. He had not stolen the money; he had simply taken it, just as a man would pick up firewood in a forest. And that was how the world aboveground now seemed to him, a wild forest filled with death, stalked by blind animals.
俺は自由なんだ! ミセス・ウーテンからもらっていたほんの数ドルを大切に抱え込んでいたことを彼は思い出した。この地下から飛び出して、自分の発見を世界に向かってわめきたかった。
ようやく笑いを抑え込んで、洞穴の土壁のすべての面に糊を塗りたくり、緑の紙幣を貼りつけていった。それが済むと、部屋の真ん中に立ち、驚嘆の目で眺めた—— 壁はどこも、曰く言いがたい黄色っぽい緑色の炎に燃え立っていたのだ。そう、この部屋が主たる隠れ場所となるだろう。自分と、自分を切り捨てた世界とのあいだには、このすべてをあざ笑う象徴が立っている。俺は金を盗んだんじゃない。ただ取ったんだ、人が森のなかでたきぎを拾うみたいに。そして上の世界はいままさにそのようなものに思えた。野生林—— 死に満ちていて、盲目の動物たちがうろついている。
洞穴の壁に高額紙幣を貼りつけ、高級な腕時計を吊し、地面にダイアモンドをばらまいて踏みつける。このシュールな、自分独自の意味だけで組み立てた閉ざされた世界のなかで、ダニエルズは新しい境地にたどり着く。それは、人生に生きる意味などまったくないと考える境地だ。黒人だろうが白人だろうが関係ない。誰もが、死に満ちた森を、何も見ずにさまよっているだけ。この認識を、ダニエルズは人々に、彼を拷問した刑事たちにすら、教えてやりたいと考え、ついに地上に出て行く……。
要するに、黒人文学の本格的な始動者として持ち上げられた反面、「抗議文学」の枠から抜けられないことを批判されもしたリチャード・ライトは、実のところ、幻の第二作において、すでに人種問題を突き抜けたところまで行っていたのだ。
では、フレッド・ダニエルズの到達するこの心境は、リチャード・ライトその人の心境だろうか。『アメリカの息子』における社会の犠牲者ビガー・トマスがライトその人ではなかったのと同じように、おそらくそうではあるまい。そのことは、この本に併録された長いエッセイからも窺える。“Memories of My Grandmother”(祖母の思い出)と題されたこのエッセイ、題から見て、祖母を偲び幼年期を懐かしむ回想録かと思いきや、祖母が宗教の色眼鏡で世界を見ていたことを—— というか、見ていなかったことを—— を暴くのが主眼になっている。祖母はキリスト教の教義(と彼女が考えたもの)を厳格に適用して生活のすべてを規定し、その結果、家族は聖書以外の本すら読むことを許されなかった。『地下で生きた男』の主人公ダニエルズも、人生は無価値だという視点からすべてを規定する。祖母もダニエルズも、個々人の性格や境遇の違いはいっさい無視する。その世界観は決定的に損なわれているのだ。
とはいえ、この小説を読む我々は、そういうダニエルズを、遠くから冷ややかに見ているわけではない。そこは、ライトがエッセイのなかで祖母をおおむね冷ややかに見ているのとは違う。強烈な違和感を覚えながらも、我々はダニエルズの視点を共有し、ダニエルズが見るものを見、彼が感じることを感じる。それが可能になるのは、やはり強烈な第一部があって、ダニエルの人格が損なわれる凄絶な体験を目のあたりにしているからだろう。短篇版ではその部分を欠いているため、彼は読み手にとってあくまで謎の他人にとどまる(「男」と呼ばれるだけで、名を与えられていないのも示唆的だ)が、完全版では我々はダニエルズになることができる。なった上で、一歩引いて自分を外から見るように彼を見ることができるのだ。むろんそうできたからといって、自分がより高潔で正しい人間になった気になってはいけないが、少なくとも、他人になってみることを可能にしてくれる言葉の力には感嘆していいと思う。
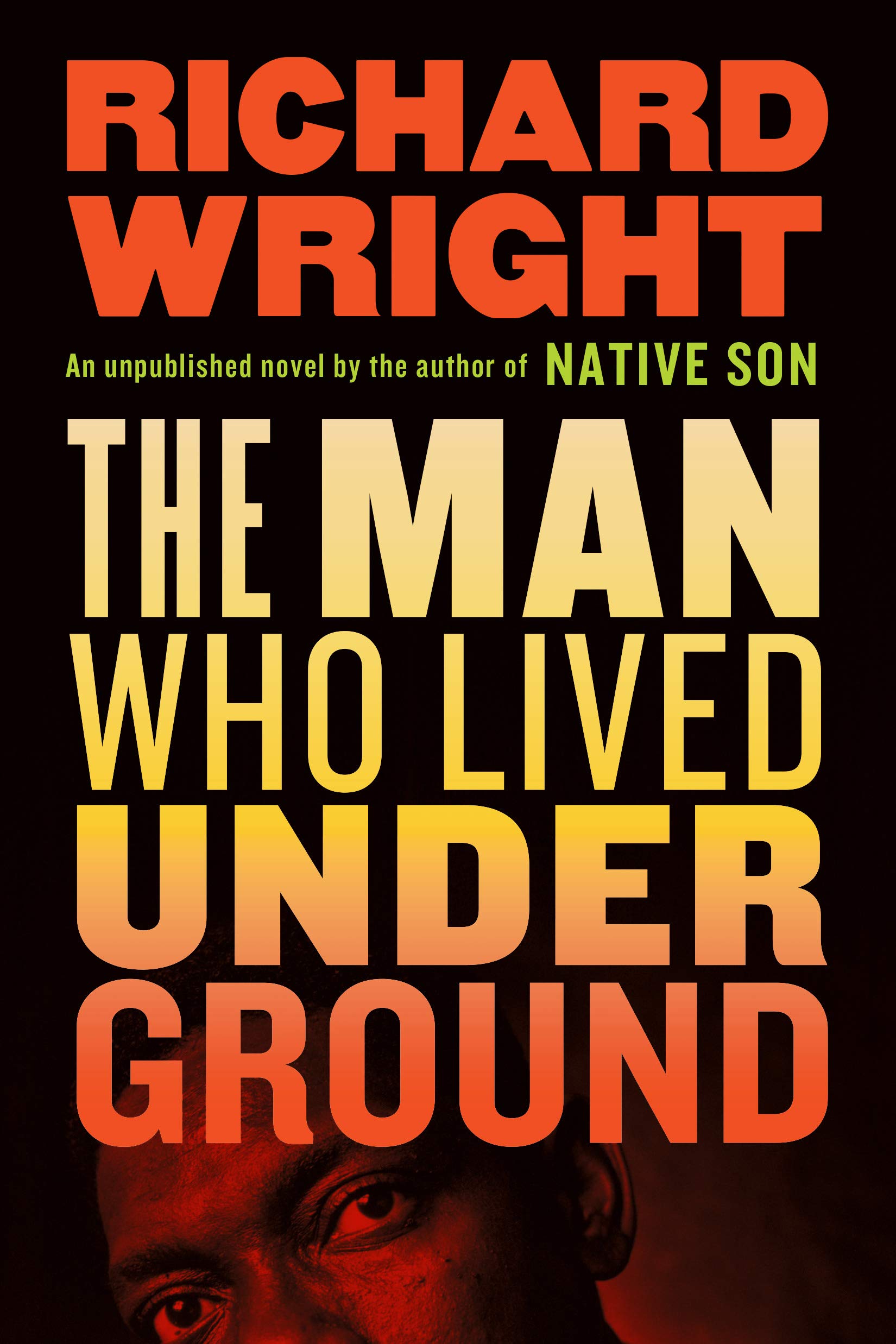
最新情報
〈刊行〉
MONKEY23号「ここにいいものがある」(岸本佐知子・柴田元幸短篇競訳)発売中。
MONKEY24号「イッセー=シェークスピア」6月15日発売。
村上春樹との共著『本当の翻訳の話をしよう 増補版』(2019年スイッチ・パブリッシング刊『本当の翻訳の話をしよう』増補改訂版、新潮文庫)、6月24日発売。
マシュー・シャープ、柴田訳『戦時の愛』(スイッチ・パブリッシング)、6月30日発売。
柴田編訳『英文精読教室』、第1巻「物語を楽しむ」、第2巻「他人になってみる」(研究社)発売中。
〈イベント〉
6月20日(日)午後2時~、MONKEY vol. 24刊行記念 柴田元幸+イッセー尾形 トーク&朗読会
6月26日(土)午前10時~、バリー・ユアグロー+川上未映子 ユアグロー『ボッティチェリ』刊行一周年記念イベント
詳細は ignition galleryホームページ で
6月27日(日)午後7時~8時、手紙社主催毎月恒例オンライン朗読会
詳細は後日手紙社ホームページにて
7月17日(土)午後1時~3時、神戸市外国語大学(+オンライン)でシンポジウム「ジャック・ケルアックの『オン・ザ・ロード』への旅」
(7月17日夜は元町映画館でトーク予定)
〈その他〉
ジェームズ・ロバートソン超短篇「ある夜、図書館で」手書き拙訳稿の入ったトートバッグをignition galleryで販売中。
バリー・ユアグロー超短篇「旅のなごり」手書き拙訳稿を包装紙にしたサンドイッチを、三軒茶屋のカフェnicolasで販売中。

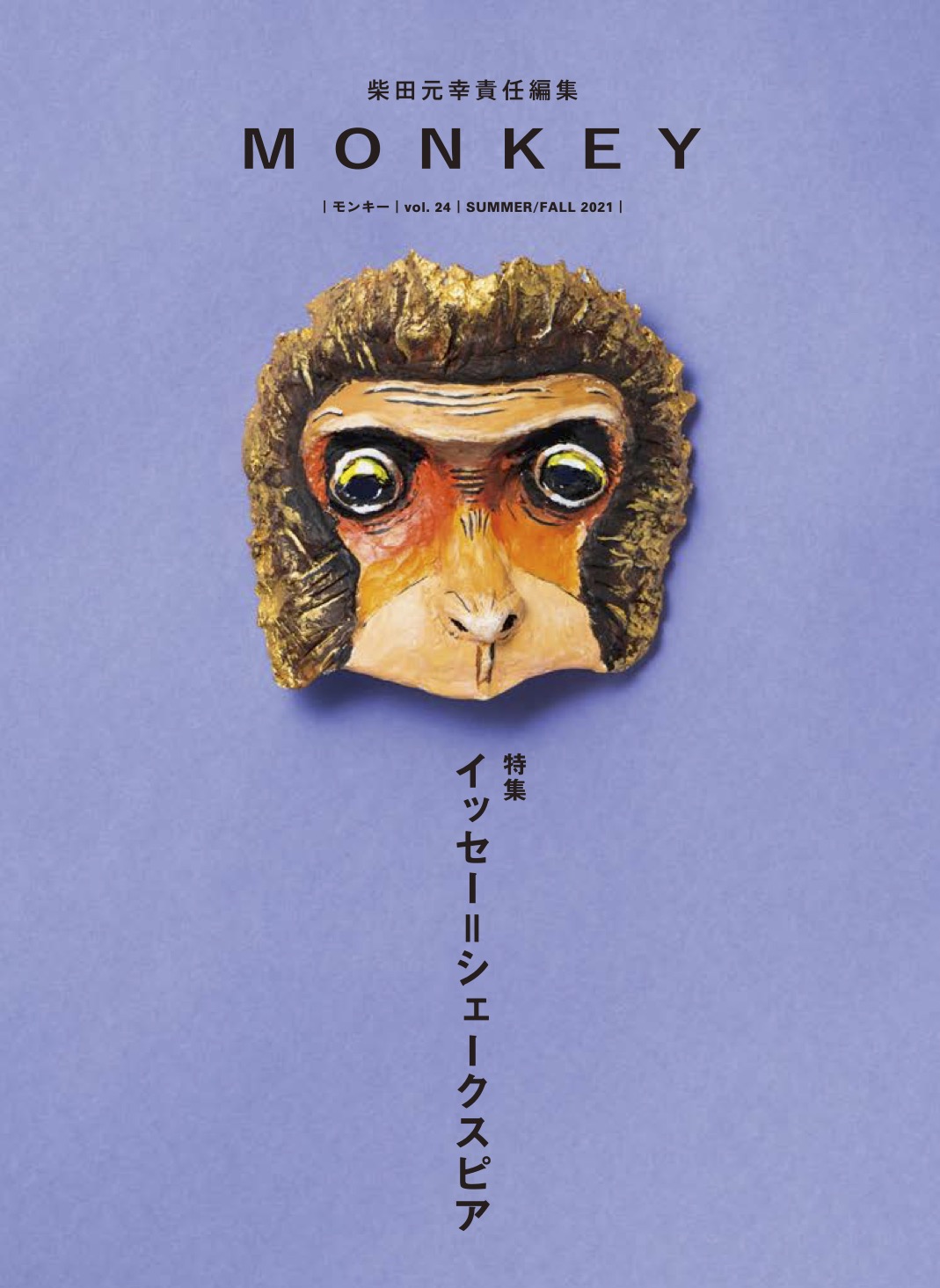





















Her motors stopped altogether and I could hear the sound of branches cracking and snapping off below her landing gear. I could see her plain now, all silver and shining in the light of the fire with T. W. A. in black letters under her wings. She was sailing smoothly out of the Square when she hit the high power lines that follow the Birmingham highway through the town. It made a loud crash. It sounded like the wind blowing the door of a tin barn shut. She only hit with her landing gear, but I could see the sparks flying, and the wires knocked loose from the poles were spitting blue sparks and whipping around like a bunch of snakes and leaving circles of blue sparks in the darkness.
The plane had knocked five or six wires loose, and they were dangling and swinging, and every time they touched they threw off more sparks. The wind was making them swing, and when I got over there, there was a crackling and spitting screen of blue haze across the highway. I lost my hat running over, but I didn’t stop to look for it. I was among the first and I could hear the others pounding behind me across the grass of the Square. They were yelling to beat all hell, and they came up fast, pushing and shoving, and someone got pushed against a swinging wire. It made a sound like when a blacksmith drops a red hot horseshoe into a barrel of water, and the steam comes up. I could smell the flesh burning. The first time I’d ever smelled it. I got up close and it was a woman. It must have killed her right off. She was lying in a puddle stiff as a board, with pieces of glass insulators that the plane had knocked off the poles lying all around her. Her white dress was torn, and I saw one of her tits hanging out in the water and her thighs. Some woman screamed and fainted and almost fell on a wire, but a man caught her. The sheriff and his men were yelling and driving folks back with guns shining in their hands, and everything was lit up blue by the sparks. The shock had turned the woman almost as black as the nigger. I was trying to see if she wasn’t blue too, or if it was just the sparks, and the sheriff drove me away.
エンジンがすっかり止まって、飛行機の脚の下で枝がバリバリパチパチ折れる音が聞こえた。もういまではすごくはっきり見えた。焚火の炎に照らされて機体がピカピカ銀色に光って、翼の裏側に黒い字でTWAと書いてあった。広場からすうっと上手く出ていったと思ったら、町を通ってバーミングハム街道ぞいにのびている高圧線にぶつかった。ガシャーン、と大きな音がした。納屋のブリキの扉が風で閉まったみたいな音だった。ぶつかったのは脚だけだったけど火花が飛ぶのが見えたし、電線が電柱からもぎ取られて青い火花を吐き出し、蛇の群れみたいにくねくね回って闇のなかに青い火花の輪を残していった。
五本か六本電線がもぎ取られぶらぶら垂れて、電線同士が触れるたびにまた火花が飛び出た。風で電線が揺れて、そっちへ行ってみるとパチパチブツブツ鳴る青いもやの幕が街道のあたりを覆っていた。駆けていく最中にぼくは帽子を飛ばされたけど止まって拾いはしなかった。ぼくは真っ先に着いた一団のなかにいて、ほかの連中がどすどす広場の芝の上を駆けてくるのが聞こえた。みんな地獄の鬼よりすごい声でわめいて、押しあいへしあいしながらぐんぐん駆けてきて、誰かが押されて揺れる電線にぶつかった。ジュッ、と鍛冶屋が真っ赤に焼けた蹄鉄を水の入った樽に落として湯気が上がるときみたいな音がした。肉が燃える匂いがした。人間の肉が燃える匂いを嗅いだのは初めてだった。そばに寄ってみたら女の人だった。即死だったにちがいない。水たまりのなかに板きれみたいにコチコチになって倒れていて、電柱からもげたガラスの絶縁体のかけらが周りじゅうに転がっていた。白いドレスが破れて、おっぱいの片方が水のなかに垂れて太ももが両方見えていた。別の女の人が悲鳴を上げて失神して電線の上に倒れそうになったけど男の人がつかまえてやった。部下たちを連れた保安官が大声でわめきながらピカピカの銃を振り回して野次馬を追っ払い、何もかもが火花に青く照らし出されていた。感電のせいで女の人はニガーとほとんど同じくらい黒くなっていた。青くもなってるのか、それとも青いのは火花だけなのか、見てみようとしたけど保安官に追っ払われた。