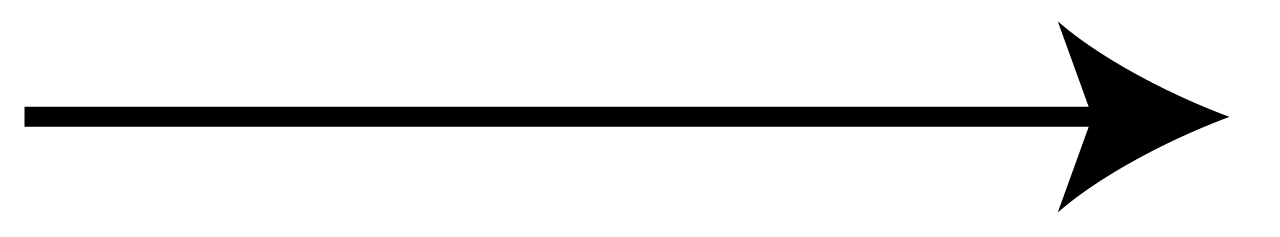ジェリー・ロペスとイヴォン・シュイナード。海の伝説とフィールドの伝説がいま、パタゴニアを舞台にして結ばれている。かつて雑誌『Coyote』に寄稿された、愛すべき友人の横顔を語ったジェリー・ロペスのエッセイを再録する。
写真=大河内禎
協力=パタゴニア日本支社
2005年、気の合う仲間と一緒に、チリへサーフトリップに行った。
僕はサーフボードと大きなバッグを抱えて、待ち合わせの空港に向かった。仲間も、ウェットスーツや着替えでバッグを膨らませている。
ところが、一人だけ身軽な男がいた。イヴォン・シュイナードだ。持っているものはサーフボードと小さなディパック一つだけ。2週間近い旅だというのに、ただそれだけの荷物なのだ。
僕が「イヴォン、荷物は?」と訊くと、彼は澄ました顔で「これだけさ」と答えた。
「これだけ?」
「ああ」
信じられなかった。
あまりにも持ち物が少ないと、逆にデイパックの中身が気になりはじめた。
「何が入ってるんだい?」と僕が訊けば、イヴォンはひとこと「釣りの道具だよ」と答えた。
「着替えは?」
「もう着てるじゃないか」
これがパタゴニアのスタイルなのだ。シンプル、ストロング、イージー。衣服が汚れたとしても、夜に洗えば朝には乾いてきれいになっている。それをまた身に着ければいいというわけだ。
着るものだけではない。彼はすべてに対してシンプルなアプローチをする。その在り方は、少々僕には驚きだった。
この旅の最中、イヴォンと相部屋になったことがあった。しかし部屋にはダブルベッド一つしかない。すると彼は「ベッドで寝たくない」と言い張った。「床が好きなんだ」と言うのだ。その言葉通り、彼は床で眠った。彼にはベッドが柔らかすぎた。
そもそも、なぜイヴォンと知り合うことになったのか。
1994年にオレゴンに引っ越してきてから、僕は本格的にスノーボードを始めた。スノーボードの連中が口を揃えて言うことは、「アンダーウェアならパタゴニアがベスト」なのだ。試してみると、なるほど本当だ。暖かいうえに、肌ざわりがいい。そういえば、初めてオレゴンでスノーボードに行ったときに、妻が買ってくれたジャケットもパタゴニアだった。あるとき、妻が言った。
「パタゴニアと一緒に何か始められるんじゃない」
ハワイ在住の妻の友人に電話した。その友人がイヴォンの知り合いだったからだ。「仕事というわけじゃなく、友達みたいな感じでパタゴニアと何かできるだろうか」と相談すると、彼はすぐに同意してくれ、イヴォンに連絡してくれると言った。
しばらくして、ある日、家の電話が鳴った。
「イヴォン・シュイナードです」
電話口の相手は言う。戸惑いながらも話は最初から弾んでいった。僕が「パタゴニアを気に入っている」と言うと、彼の声が嬉しそうな響きになったことをよく覚えている。
半年ほどたったある日、イヴォンから電話があった。
「サンタバーバラの自宅に遊びにこないか」と誘われた。その翌週には僕はイヴォンの家のリビングにいた。アロハシャツのデザイナーやサーフィンマガジンの編集者など、いろいろな人が集まっていた。僕はそこで、マウンテンカンパニーというパタゴニアのイメージを、オーシャンにも広げていく可能性について意見を求められた。
「すでに多くのサーファーがパタゴニアの製品を愛用している」
僕は言った。「特に大人のサーファーはパタゴニアの良さをわかっている」と。
イヴォンは「そのイメージを広げていきたい」と言い、言葉を続けた。
「オーシャン・アンバサダーになってくれないか」
僕は「もちろん喜んで」とすぐ言葉を返した。
この日からイヴォンと彼の妻マリンダとの付き合いが始まったのだ。人々の目を環境に向けさせるためにパタゴニアという会社がある。最良の製品をつくることに力を注ぐという、彼のポリシーは、僕にも共通することだった。だから僕はパタゴニアと一緒に働くことに決め、現在はオーシャンのデザインをも担当している。
彼らのやり方はとてもイノベイティブだ。環境を考慮した作り方で費用もかかるけれど厭わない。その目的意識が僕をひきつける。そして、そんな魅力的なパタゴニアが、イヴィンそのものなのだ。パタゴニアは僕が働く最後の会社になるような気がしている。
僕とイヴォンの交流を知っている人から、ときどきイヴォンの人物像を訊かれることがある。そのたびに僕は「普通の人だよ」と答える。そう、彼はきわめて「普通」の人なのだ。有名企業を経営しているような感じにはとても見えない。あるときイヴォンは、サーフィンがうまくなるコツはと、ある若者に訊ねられたことがある。彼はこう言った。
「何度も波に乗ること」
単純だが大切なことだ。当たり前のことを当たり前のこととして考える。イヴォンはそういう「普通」の頑丈な男だ。「好きになること」と僕は彼の言葉に付け加えたい。
彼は自然の中に身をおくことを誰よりも望んでいる。家や会社の中に閉じ込めておくことはできない。ゴツゴツした木の根元に座っていたり、野宿したりしている時のほうが、よほど快適なのだ。ひょっとしたら、薄暗い洞窟の中でさえも、家の中より落ち着くのではないだろうか。だってイヴォンは常にフィールドに身をおき、風や焚火、夜露や川のせせらぎと会話しているのだから。
僕にとって、彼は兄のような存在だ。いつも身軽で少年のような心を保ち、フィールドをこよなく愛する男。それがイヴォン・シュイナードだ。
NEXT :
賢者の教え