
毎月、猿が仲間に「ここにバナナがあるぞー」と知らせるみたいな感じに、英語で書かれた本について書きます。新刊には限定せず、とにかくまだ翻訳のない、面白い本を紹介できればと。
ハムネット? ハムレットじゃないの? と多くの読者は思うことだろう。だが、ノー、アイルランド生まれで現在はスコットランドに住む作家、マギー・オファレル2020年の小説のタイトルはHamletではなくHamnetである。
あ、そう、じゃそれ、ハムレットをもじった笑えるパロディ? と同じく多くの読者は思うのではないか。だが、これもノー。たしかにハムレットと大いに関係はあるが、もじり、というようなものではとうていなく、それ自体の力強さを備えた本格長篇である。
まず、歴史的事実を少し。ウィリアム・シェークスピアには子供が3人いた。長女のスザンヌ、そして双子のジュディスとハムネット。スザンヌとジュディスは無事に育って成人したが、ハムネットは疫病の犠牲となって11歳で亡くなった。1596年8月のことである。
父ウィリアムが『ハムレット』を書いた年は特定できないが、1600~1601年と推定される。つまりシェークスピアは、死んだ一人息子の名を冠した芝居を(当時の戸籍ではHamletとHamnetという名は交換可能、つまり事実上同じ名だった)、息子が亡くなった4~5年後に書き、自分の劇団で上演したのである。
それはいったいどういうことなのか? シェークスピアはどういう気持ちでハムレットをハムレットと名づけ、『ハムレット』を書いたのか? この疑問が、マギー・オファレルがこの小説を書いた背後にあったという。
ならばオファレルは、この小説で、息子を失ってから『ハムレット』を書くまでの、シェークスピアの内面を深く掘り下げて描いているのか? これまた答えはノー。この小説の大半、中心に位置しているのは彼の妻アグネスであり、我々はシェークスピアのことも、アグネスの目を通して見る。
ハヤブサをいつも肩に乗せている謎めいた娘アグネスが、全然学ぶ気のない近所の子供にラテン語を教えることしか能のないパッとしない年下の男を見初め、その家に嫁ぐ。だが一旗揚げようと夫がロンドンに出て行ってからは、夫は一個の謎と化す。彼の心の中が我々にも見えてくるのは、ようやく最後の10ページ、ちょっと神業と言いたくなるほど見事なクライマックスにおいてである。
(ちなみに現実のシェークスピアの妻は通常アン・ハサウェイと呼ばれるが、作者オファレルによれば父親の遺書の中では「アグネス」と記されているのでこの名を採用したという。もうひとつちなみに、オンラインで読めるこの本の書評のほとんどがAgnesは「アニス」と読む、と指摘しているが、オンラインで見られる複数のインタビューやトークで作者自身は「アグネス」と発音しているので、ここではアグネスで通すことにする。)
現実のシェークスピアは妻アン/アグネスと子供3人、そして老いた両親をストラトフォードに残しロンドンに出ていき、演劇で成功を収め、ストラトフォードには時おり戻ってきて、離れていても仕送りはきちんと欠かさず、家族のために大きな家も購入した。
オファレルはこうした伝記的事実をほぼそのまま使いながら、決して史実の重みにおんぶしていない、独自の磁力がはたらいている世界を作り上げている。その磁力を作り上げているのは、何と言っても見事な文章である。僕は英語の本を読んでいていい文章だと思うとつい声に出して読んでしまうのだが、この本はほとんどどこも声に出したくなる文章だった。出だしはこんな感じである:
A boy is coming down a flight of stairs.
The passage is narrow and twists back on itself. He takes each step slowly, sliding himself along the wall, his boots meeting each tread with a thud.
Near the bottom, he pauses for a moment, looking back the way he has come.
Then, suddenly resolute, he leaps the final three stairs, as is his habit. He stumbles as he lands, falling to his knees on the flagstone floor.
It is a close, windless day in late summer, and the downstairs room is slashed by long strips of light. The sun glowers at him from outside, the windows latticed slabs of yellow, set into the plaster.
He gets up, rubbing his legs. He looks one way, up the stairs; he looks the other, unable to decide which way he should turn.
The room is empty, the fire ruminating in its grate, orange embers below soft, spiralling smoke. His injured kneecaps throb in time with his heartbeat. He stands with one hand resting on the latch of the door to the stairs, the scuffed leather tip of his boot raised, poised for motion, for flight. His hair, light-coloured, almost gold, rises up from his brow in tufts.
There is no one here.
一人の男の子が、階段を降りてくる。
段は狭く、折れ曲がっている。男の子は一段ずつゆっくりと、壁に沿って滑るように降り、ブーツが一歩ごとにドスッ、ドスッと音を立てる。
底近くまで来て、一瞬止まり、来た方をふり返る。それから、一気に決意を固めて、最後の三段を、いつもの習慣どおりぴょんと飛び降りる。よろめいて着地し、板石の床に膝をつく。
夏も終わりに近い、風もなく蒸し暑い日。階下の部屋には、光の長い帯が切り込みのようにのびている。太陽が外から男の子を睨みつけ、窓はさながら、黄色い格子模様の石板が石膏に組み込まれたよう。
男の子は立ち上がり、両脚をさする。目をまず一方、階段の上に向ける。それからもう一方に向け、どっちに向かうべきか決めかねている。
部屋は空っぽで、暖炉の火は格子の中で思いをめぐらし、柔らかな、螺旋を描く煙の下に橙色の燃えさしが見える。傷めたひざ頭が心臓の鼓動に合わせて疼く。男の子は片手を、階段に通じる扉の掛け金に置く。ブーツの先っぽの、革が擦り切れた部分は持ち上がり、いまにも動き出そうと、逃げ出そうと構えている。明るい色の、ほとんど金色というに近い髪が、いくつかの房となって額から上がっている。
ここには誰もいない。
この小説では、丁寧な描写は物語を停滞させない。描写自体が物語だからだ。進めたい物語は決まっていてそれに程よい描写を加えて肉付けするのではなく、描写の中から次の展開が自然に生じてくる—— あくまで印象にすぎないが、読んでいてつねにそういうふうに感じられて、非常に快い(もちろん、ハムネットを亡くしたアグネスと娘たちが感じる悲しみは本当に悲痛であり、単に「快い」では済まないのだが)。最終的には、『ハムレット』に関する新しい解釈も提示され、その解釈も非常に興味深く説得力もあるけれども、読んでいる時間の大半は、シェークスピアや『ハムレット』のことはほとんど忘れて、描写/物語自体の見事さに浸っていることができる。
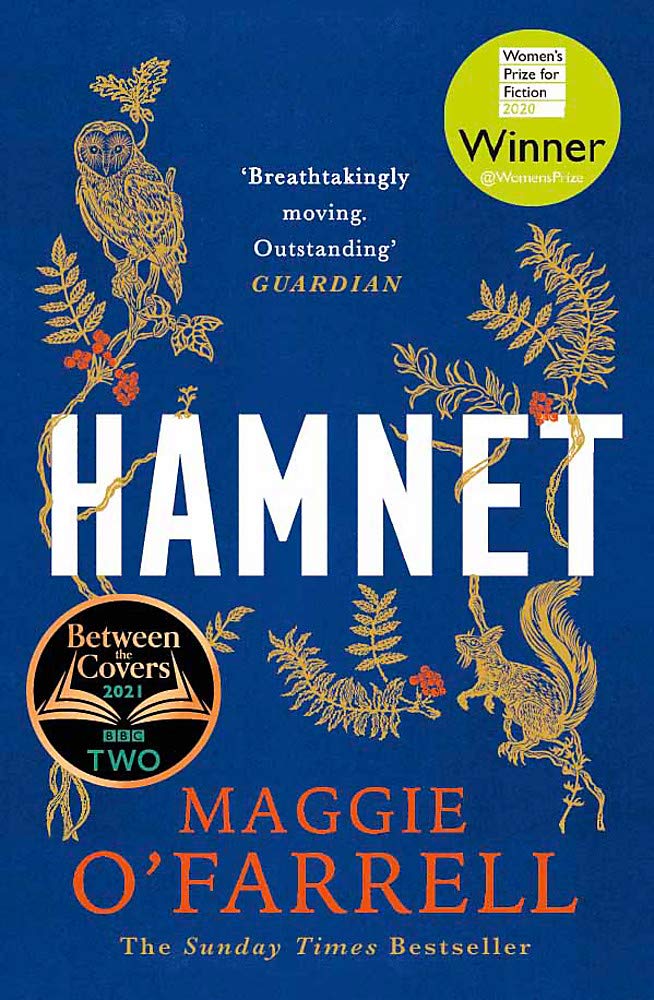
✴︎
『ガリバー旅行記』(1726)の第3部冒頭で、巨人国への旅から帰ってきて間もないガリバーは、知り合いから好条件で誘われ、異国を見たいという思いがまた頭をもたげ、船医としてふたたび旅に出ることにする。
The only Difficulty that remained, was to persuade my Wife, whose consent however I at last obtained by the prospect of Advantage she proposed to her children.
残る唯一の困難は、妻を説得することでしたが、これも何とか、子どもたちの将来に有利になるから、ということで同意を取りつけました。
夫が冒険の旅に出る上での、ささやかな障害でしかない妻。これは現代の女性作家が黙っちゃいないだろうなあ、と思っていたら案の定、オーストラリアの歴史小説家ローレン・チェイターが、このガリバーの妻、『ガリバー旅行記』の冒頭で「ニューゲート街でメリヤス商を営むエドモンド・バートン氏の次女メアリを娶り、持参金400ポンドを得ました」と記されたのみの女性に焦点を当てた小説『ガリバーの妻』を発表した。プロローグのあと、本篇の書き出しは:
Wapping, London
April, 1702
‘Widow Gulliver, is it true your husband once saw a monster?’
Everybody turns and Mary’s cheeks grow hot under the hawkish scrutiny of a dozen pairs of eyes. The confinement room above Stewart’s bakery seethes with gossips. Some are Sal Stewart’s neighbours, but others hail from further afield – Sal’s sister, for instance, who has travelled from Dorset on the coach. Ranged about on sofas and chairs, they are waiting, expectant, wine glasses half-raised to parted lips.
Mary frowns at the bed where she is knuckle-deep in Sal’s privities. The presence of gossips is an unfortunate necessity. Should Sal’s infant die, their testimony will protect her from whispers of murder and witchcraft. Mary is so used to performing her tasks in front of an audience that the intrusion of voices doesn’t often bother her. Today she wonders if the benefit is worth the fuss.
‘Perhaps,’ she mutters. ‘I cannot say. I wasn’t there.’
ロンドン、ウォッピング
1702年4月
「ガリバー未亡人、あなたのご主人がかつて怪物を見たって、本当なんですか?」
みんながこっちを向き、二ダースの鷹の目のような凝視を浴びてメアリの頰が熱くなる。スチュアート家が営むパン屋の階上の出産部屋は、お喋りに興じる連中でやかましいことこの上ない。サル・スチュアートの隣人もいるが、もっと遠くから来ている者もいる。たとえば、乗合馬車でドーセットからやって来たサルの姉。みんなソファや椅子に座って、待っている。開いた唇にワイングラスをなかば持っていき、待ち構えている。
寝台にいる、手を指関節までサルの陰部に入れたメアリは、眉間に皺を寄せる。お喋り連中の存在は、いわば必要悪である。もしサルの赤ん坊が死産だったら、彼女が殺人も呪術もやっていないことを彼らが証言してくれる。メアリも人前で仕事をすることには慣れっこなので、ガヤガヤ声が入り込んできてもたいていは気にしない。だが今日は、有難味と鬱陶しさ、どっちが重いか首を傾げたくなる。
「どうでしょうか」彼女は呟く。「何とも言えません、私はその場にいませんでしたから」
「その場」とは夫ガリバーが見聞きしてきた異国の、驚異と冒険に満ちた場である。そしてその場にいなかったメアリがどこにいたかといえば、言うまでもなく、ロンドンのありふれた日常である。小説が始まった時点では、ご覧のとおり「未亡人ガリバー」と言われているように、夫レミュエルは異国で亡くなったものと思われていて、メアリは夫のいない暮らしに満足している。助産師として働いて一人娘を育て、完全に自立していられるのだ。そこへ、亡くなったと思われていた夫が帰ってきたとき、それは鬱陶しい厄介事でしかない。
この小説でのレミュエル・ガリバーは、不誠実で、噓つきで、自分勝手で、利己的で、何の魅力も(悪人が往々にして持つ逆説的な魅力も)ない人物である。日々の仕事を黙々とこなしている妻の許に夫が時たま帰ってくる、という構図は『ハムネット』と同じだが、ハムネットの妻にとって夫が一個の、苛立たしくはあれ考えずにはいられない謎であったのに対し、メアリにとっての夫は、諸悪の根源以外の何ものでもない(優しさ、思慮深さなど男性が持ちうる肯定的な側面は、メアリが本当は結婚したかった—— だがガリバーの策略で遠ざけられてしまった—— 知人リチャードが全部担っている)。ものすごく小さな人間を見てきたんだ、などと夫が訴えても、メアリにとっては煩わしい雑音にすぎない。
物語の大半、夫レミュエルはメアリとその娘エリザベスと同じ屋根の下にいるわけだが、彼らのあいだにほとんど交流はない。たまに夫が登場しても、何やら自分勝手な文句を呟くだけで、またすぐ飲み屋に行ってしまう。一方メアリは助産師として、助産の仕事を女から奪おうとする男性医師たちとも闘うことを強いられながら、娘にも何とか自立の大切さを教えようと努める。その不平等な戦いは、家庭に何ら貢献しないのに法律上は夫が絶対的な権力を妻に対して持っているという構図の延長線上にある。
読んでいて何度も、もう少し夫が登場して喋ったら話はもっと面白くなるのに、と思ったが、おそらく作者はそれだけは絶対やるまいと決めているのだろうな、とも思った。これまで300年、読者はひたすら夫の声を聞いてきたのであり、今度は妻の声を聞く番だ、と。プロモーションビデオを見たら、作者はまさにそう言っていた。
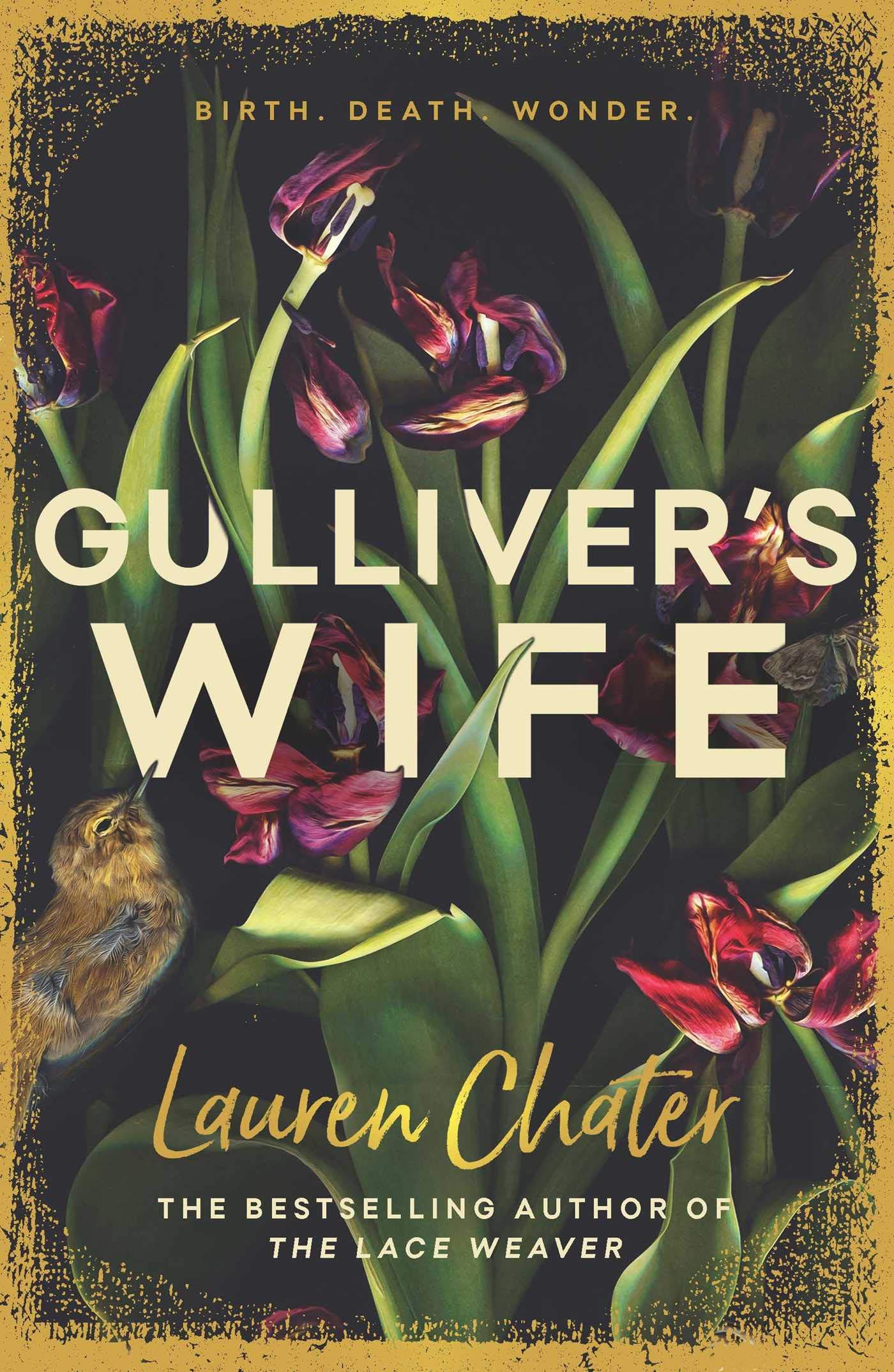
✴︎
ジキルとハイドの物語を家政婦の目で語るヴァレリー・マーティン『メアリー・ライリー』(1990)、エイハブ船長の妻の物語であるSena Jeter Naslund, Ahab’s Wife(1999)、失踪した(つもりの)夫を見守り続けるエドゥアルド・ベティ『ウェイクフィールドの妻』(1999)等々、「女性の視点からの語り直し」は20世紀末から目につきはじめたが、まだまだ新しい可能性はありそうである。
最新情報
〈刊行〉
MONKEY24号「イッセー=シェークスピア」発売中。
村上春樹との共著『本当の翻訳の話をしよう 増補版』(2019年スイッチ・パブリッシング刊『本当の翻訳の話をしよう』増補改訂版、新潮文庫)、発売中。
マシュー・シャープ、柴田訳『戦時の愛』(スイッチ・パブリッシング)、7月5日発売。
柴田編訳『英文精読教室』、第1巻「物語を楽しむ」、第2巻「他人になってみる」(研究社)発売中。
〈イベント〉
6月26日(土)午前10時~、バリー・ユアグロー+川上未映子 ユアグロー『ボッティチェリ』刊行一周年記念イベント
詳細は ignition galleryホームページ で
6月27日(日)午後7時~8時、手紙社主催毎月恒例オンライン朗読会
詳細は手紙社ホームページにて
7月10日(土)午前11時~、マシュー・シャープと『戦時の愛』刊行記念トーク・朗読(通訳つき)。
7月17日(土)午後1時~3時、神戸市外国語大学(+オンライン)でシンポジウム「ジャック・ケルアックの『オン・ザ・ロード』への旅」
(7月17日夜は元町映画館でトーク予定)
〈その他〉
ジェームズ・ロバートソン超短篇「ある夜、図書館で」手書き拙訳稿の入ったトートバッグをignition galleryで販売中。
バリー・ユアグロー超短篇「旅のなごり」手書き拙訳稿を包装紙にしたサンドイッチを、三軒茶屋のカフェnicolasで販売中。

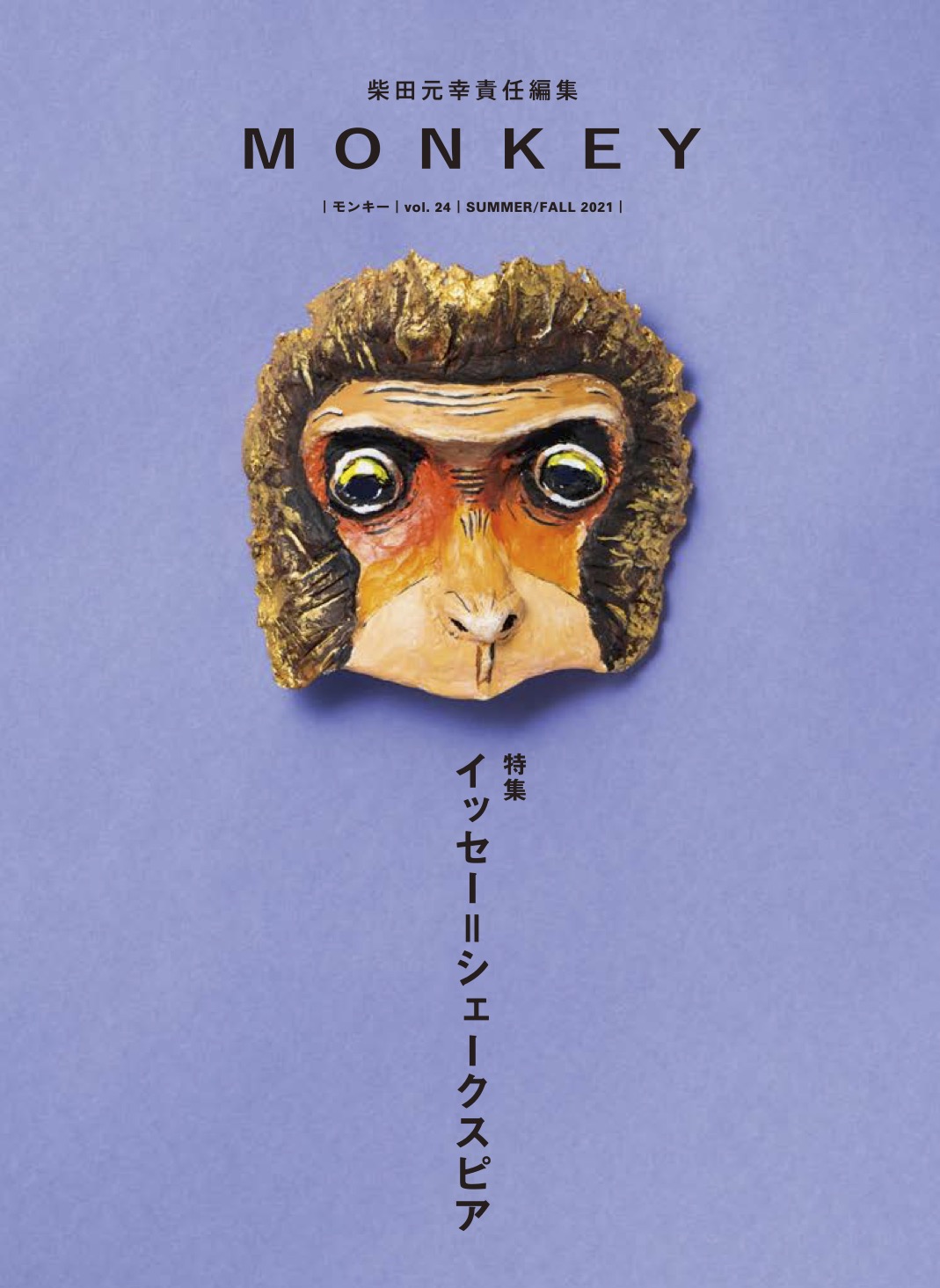





















2)Lauren Chater, Gulliver’s Wife(2020, Simon & Schuster)