
毎月、猿が仲間に「ここにバナナがあるぞー」と知らせるみたいな感じに、英語で書かれた本について書きます。新刊には限定せず、とにかくまだ翻訳のない、面白い本を紹介できればと。
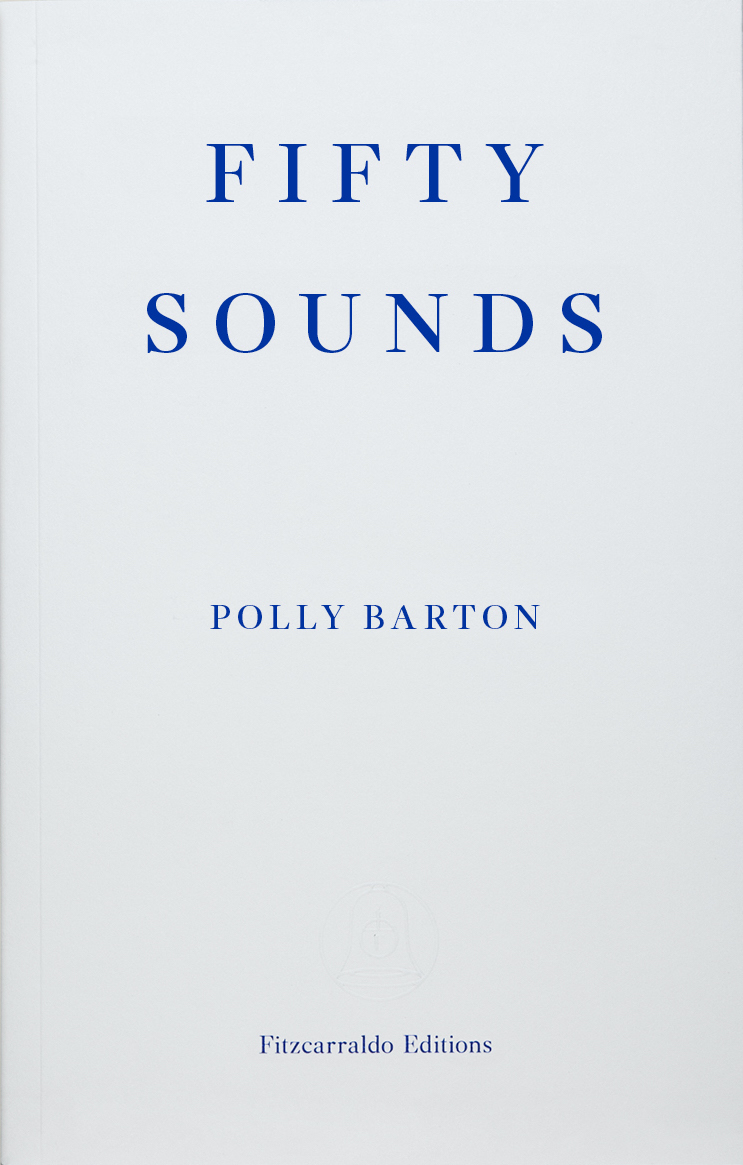
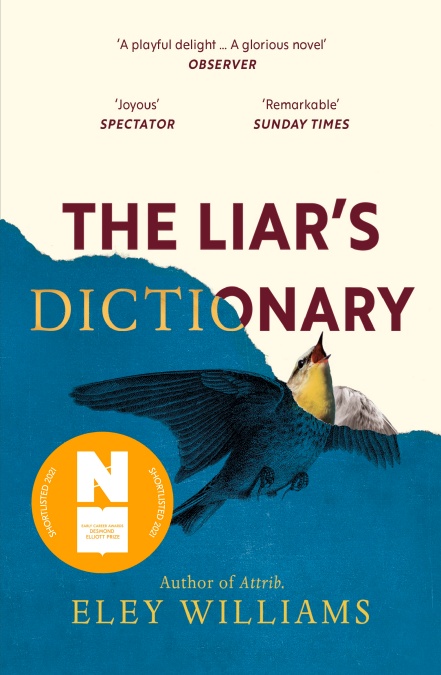
Fifty Soundsの著者ポリー・バートンは日本文学の翻訳者。現在もっとも優れた若手の現代日本文学翻訳者の一人である。柴崎友香、松田青子、津村記久子などを翻訳していると言ったら、その見識の確かさが伝わるだろうか。
Fifty Soundsとは日本語の「五十音」のことである。パラパラめくってみると、<giro’>, <giza-giza>, <zara-zara>といった擬声語が見出しのように掲げられ、それぞれのあとに1~10ページくらいの文章が続く。
とするとこれは、優れた翻訳者による、エピソードや逸話を交えた「ひと味違う擬声語辞典」だろうか?
まあ、そう言えなくもない。言えなくもないが、ただし「違う」のは「ひと味」では済まない。二味も、三味も違うのである。
まず、それぞれの見出しには、辞書っぽく定義のようなものが添えられているのだが、これがなかなか奇妙である。たとえば——
☞giro’: the sound of eyes riveting deep into holes in your self-belief, or vicariously visiting the Nocturama, or every party where you have to introduce yourself
(ジロッ:目があなたの自信に深く食い込む音、もしくは他人の身になって夜のパノラマを訪れる音、または自己紹介をさせられるすべてのパーティの音)
☞muka-muka: the sound of nights with a dictionary, and the thrill of drawing close to someone’s real feelings
(ムカムカ:辞書のある夜の音、誰かの本音に迫る戦慄の音)
☞pika-pika: the sound of my floors and your trainers and our graveyards
(ピカピカ:わたしの床とあなたのトレーナーとわたしたちの墓場の音)
ひょっとしたら言葉の本質を衝いているような気もするが、とにかくいわゆる「辞書的に妥当」なものでないことは確かである。
実際、少し読み進めれば、この本を読む楽しみのひとつは、こういう一見muri-muriな「定義」が、なるほどこの人にとってはこの上なく真なのだ、と納得していくことにあると言ってもいい。
書かれていることの多くは、ある擬声語にどういう状況で出会ったか、あるいはその擬声語の有効性をどういう状況で実感したか、その具体的な記述である。といっても、これは単純に体験談に終始する本ではない。たとえば ‘zara-zara’ を語る際にはまずウィトゲンシュタインの言語観が詳しく論じられたりするし、本全体、「これが日本語の特徴です」「ここに日本文化の日本らしさがあるのです」といった話に収斂する本では全然ない。ケンブリッジでウィトゲンシュタインを学んだ体験であれ、佐渡で英語教師を務めた日々であれ、著者はそういう具体的な状況において自分が何に驚き、戸惑い、ムカつき、歓喜したかを丹念に綴る。その個人的体験の手触りこそ、この本では何より大事なのである。
Sometimes words are applied to memories retroactively. Ever since learning the word pota-pota it has put me in mind of that scene. Pota-pota: the sound of water dripping, droplets falling on the floor, of crying, of flowers, fruit or other small objects falling continually. ‘Drip’ is not a desperately melancholy word in English, and nor is pota-pota in Japanese, but for me it has always seemed to carry with it the sadness of this moment. The sadness of my car crying red tears onto the gravel, and all the other sadnesses which that stood for in that moment. The sadness of being laughed at. The sadness, and the shock, maybe more than anything, of realizing what a child I was in this society, of not really feeling part even of this car crash which I had caused, participated in, been given minor whiplash by. The sadness of this life that I was living which was driven by adrenaline and sometimes reggae but had nothing to say for itself when the real world came to call, when it plied the physical world with tremendous clumsiness and was held to account. What did kissing matter when you couldn’t even drive, or have a phone, or speak Japanese? I could practically hear the policeman’s voice asking me, beneath the layer of friendly banter. Being pathetic is one thing, but why are you actively rejoicing in it?
時に言葉は、過去にさかのぼって記憶に作用する。「ポタポタ」という言葉を学んで以来、その語はいつも私をあの場面に連れていく。ポタポタ——水が垂れる音、しずくが床に落ちる音、泣く音、花、果実など小さな物体がたえず落ちる音。‘drip’(垂れる)は英語ではべつに深い憂いをたたえた言葉ではないし、日本語のポタポタも同じだが、私にとってそれは、つねにこの瞬間の悲しさを携えてきたように感じられるのだ。私の車が砂利道に赤い涙を流していることの悲しさの、そしてその瞬間それによって象徴されたほかのすべての悲しさの音。笑われることの悲しさ。この社会のなかで自分がいかに子供かを悟った悲しさと、おそらく何よりもまず衝撃、自分で起こし自分が加担し軽いムチ打ち症にまでなったこの自動車事故の一部だとすら実感できないことの。アドレナリンに、加えて時にはレゲエに突き動かされていても、いざ現実世界がやって来ると——これ以上はないというくらいぶざまに物理的世界に手を出し、その責任を問われると——自分について何ひとつ申し立てできない人生を生きていることの悲しさ。運転もできないのに、電話も持っていないし日本語も話せないのに、キスがどうこうなんて何の意味があるのかね? 友好的な軽口の下で、警官の声がそう問うているのがほとんど聞こえる気がした。情けないのはまあいい。だけどあんた、何だって、目いっぱい喜んでるんだ?
日本に来て間もないころに、自動車事故を起こしたときの体験を綴った一節である。自己憐憫に終始するかと思いきや、最後に(皮肉交じりではあれ)rejoicingという語が出てくるところが印象的だが、それはともかく、「ポタポタ」という語に関し誰にとってもおおむね妥当な辞書的定義ではなく、本人にとって切実な意味を持つ「定義」がここで提示されていることはおわかりいただけるかと思う。
だが考えてみれば、実は我々一人ひとりが、それぞれの語に対して、そういうカッコ付きの「定義」を持っているのではないか。著者はそうあからさまに主張しているわけではないが、この本を読んでいてそういうことを考えずにいるのは難しい。村上春樹さんの「僕は正しい理解というのは誤解の総体だと思っています。誤解がたくさん集まれば、本当に正しい理解がそこに立ち上がるんですよ」という発言に通じるものがここにはある。まず万人に妥当な辞書的定義がトップダウン式にあって、そこから何らかの逸脱を含んだ個人的「定義」が派生していくのではなく、それぞれの偏差を持ったバラバラな「定義」がまずあって、そこからボトムアップ式に辞書的な定義がいずれ出来てくるにすぎない。そのバラバラな「定義」が自分の中で生じる瞬間に、Fifty Soundsの著者はこの上なく敏感である。
個人的な体験を語りつつ言語について語る本、という二面性のバランスは後半ではだいぶ変わってくる。言語についても語るけれど、それはあくまで人間関係を語る上で言語が果たす役割に焦点を当てている限りにおいてであって、基本的には、著者が日本とイギリスを往復するなかで翻訳者となっていく過程をめぐるメモワールになっていく。その内容について安易な要約は避けるが、辞書的定義から逸脱した個人的「定義」を綴った前半を思えば、「ほんとうの自分」といったような正解的なものをこの人が探すわけではないことは容易に予測できるだろう。「標準」のようなものからはいろんな形でずれているかもしれないが、そのいろんな偏差やいびつさを抱えているのが自分なのだ、と納得していくような流れ。一見めまぐるしく話が変わる本だが、「正解」とは何らかの基準に適応することではなくて、自分がいるいま・ここにその都度しっくりくるもののことなのだ、とでもまとめられそうな精神においては一貫している。ただし、つねに健全な懐疑を保ちつづけるこの書き手は、そんなにあっさりまとめはしないだろうが……。
✴︎ ✴︎ ✴︎
エリー・ウィリアムズの小説『噓つきの辞書』(The Liar’s Dictionary)の真ん中あたりで、The Café L’Amphigouriという名のカフェが出てくる。
エドワード・ゴーリーのファンの方々なら、これってゴーリーの全4巻の作品集Amphigorey(1972-2007)への目配せでは?と思われるかもしれない。
実は、僕もそう思ったのです。
が、そう考えるのはあべこべである。『リーダーズ英和辞典』には次のような項がある。
am・phi・go・ry /発音記号は省略/, –gou・ri
n 〖一見意味があるようで〗無意味な文〔詩〕; パロディー.
つまり、amphigoryもしくはamphigouriと綴るれっきとした(しかも、いかにもゴーリー好みの意味を持つ)英単語があって、ゴーリーはそれを上手に借りているのですね。英語辞典の最高峰OED(Oxford English Dictionary)によれば初出は1770年。
あるいは、これはまだOEDにも載っていないmountweazelという単語がこの作品ではクロースアップされている。ほかの辞典・事典の盗用を摘発しやすくするために、辞書製作者が意図的に入れる、ありもしない単語とその語義のことである。ウィキペディアが例に挙げているのは、esquivalienceという架空の単語で、The New Oxford American DictionaryのCD-ROM第一版に掲載され、‘the wilful avoidance of one’s official responsibilities’(公式の責任を故意に回避すること)と定義されている。
——という具合に、「言語ネタ」満載の小説であり、Fifty Sounds同様、いくつもの項目に分かれていて、こちらはabc順にA is …; B is …; C is …とアルファベット絵本のような見出しになっている。
で、この形式が内容にぴったりなのである。二つの物語が交互に語られる。ひとつは現代のロンドンが舞台で、20世紀前半に刊行されて8巻まで出たものの未完に終わった辞書をデジタル化する作業に携わる若い女性マロリー(Mallory)の話。100年以上前に作成された単語の定義カードを整理していくなかで、存在しない単語がいくつも交じっていることを彼女は発見する。
We found some more fictitious words. They seemed to be getting more and more obscure but maybe that’s because my tolerance for them was becoming weaker.
Here was one about the ‘guilt of having a false speech impediment’. Here was another noun specific to ‘the dream of retiring and keeping bees’. More usefully, perhaps, Pip was very pleased to find a noun for ‘the hardened callous on your middle finger caused by years of ill-use’.
私たちはさらにいくつも虚構の単語を発見した。それらは意味もどんどん曖昧になっていくように思えたが、もしかしたらそれは私の許容力がだんだん弱ってきたからかもしれない。
たとえば、「虚偽の発話障害を装うことの罪悪感」を意味する語があった。もうひとつの名詞は、「引退して蜂を飼うという夢」という意味に特化していた。もう少し役に立ちそうなものとして、ピップは「何年も酷使したせいで中指に出来た硬い胼胝」を見つけて悦に入っていた。
——ピップとは彼女の同性の恋人にして同居人。率直で行動的な人物であり、何事も言語的に深く考えすぎて思考停止に陥りがちな主人公にとっては理想的なパートナーに思える。
もうひとつは、まさにこの辞書が製作中だった1899年のロンドンを舞台に、一人の辞書製作者に光が当てられる物語。——と言えば、この辞書製作者ピーター・ウィンスワースこそが何らかの理由で辞書に虚構の単語を潜り込ませていることは明白だろう。虚偽の発話障害を装ったのも、隠居して蜂を飼いたいと夢見ているのも、すべてウィンスワース自身なのである。
言語オタクのウィンスワースには恋人もいないが、同僚のハンサムで外向的で誰にも好かれて世渡りが上手くて頭の中はカラッポな男の婚約者ソファイアに恋をしてしまう。我ながら驚いたことに、読んでいくうちに僕にとって、この二組の女女/男女関係が興味の中心となっていった。ピップとマロリーのいい関係はそのまま続いてほしいし、ウィンスワースとソファイアが「結ばれる」のはまあ無理としても、頭カラッポ野郎になんとか一泡吹かせてほしい……と、なんとも通俗的な問題にわが関心は収斂していったのである。
だがおそらく、これこそがこの小説の強みだと思う。Fifty Soundsが、日本語、英語といった言語の細部に入念に目を向けつつ、自分が世界と、そして自分自身とどう関わるのかに関心が向いていくのと同じように、このThe Liar’s Dictionaryも、言葉にこだわった結果、逆に人間に興味が向くようになっている。さまざまな言語ネタを面白がりながらも、実はその力に牽引されて、読者は一気にこの小説を読んでしまう。少なくとも僕はそうでした。
最新情報
〈刊行〉
MONKEY24号「イッセー=シェークスピア」発売中。
村上春樹との共著『本当の翻訳の話をしよう 増補版』(2019年スイッチ・パブリッシング刊『本当の翻訳の話をしよう』増補改訂版、新潮文庫)発売中。
マシュー・シャープ、柴田訳『戦時の愛』(スイッチ・パブリッシング)発売中。
バリー・ユアグロー、柴田訳『東京ゴースト・シティ』(新潮社)9月28日刊行予定。
柴田編訳『英文精読教室』、第3巻「口語を聴く」、第4巻「性差を考える」(研究社)発売中。
〈イベント〉
9月5日(日)午後1時30分~3時、朝日カルチャーセンター横浜教室で「あやしいアメリカ文学 幻想・怪異の世界」。教室・オンライン同時開催
詳細はこちら。
9月21日(火)午後7時~8時30分、丸善ジュンク堂書店主催で『英文精読教室』「第3巻 口語を聴く」「第4巻 性差を考える」刊行記念トークイベント。
詳細はこちら。
9月25日(土)午後2時~3時、手紙社主催毎月恒例オンライン朗読会「今、これ訳してます」第17回。
詳細はこちら。
〈配信〉
コロナ時代の銀河 朗読劇「銀河鉄道の夜」 河合宏樹・古川日出男・管啓次郎・小島ケイタニーラブ・北村恵・柴田
コロナ時代の銀河——朗読劇「銀河鉄道の夜」と10年〜無観客野外朗読劇の映像公開記念(有料)
《新日本フィル》朗読と音楽 ダイベック「ヴィヴァルディ」 朗読:柴田 演奏:深谷まり&ビルマン聡平
ハラペーニョ「謎」朗読音楽映像 ウォルター・デ・ラ・メア「謎」/ハラペーニョ=朝岡英輔・伊藤豊・きたしまたくや・小島ケイタニーラブ・柴田
シンポジウム ジャック・ケルアックの『オン・ザ・ロード』への道(@神戸市外国語大学、2021/7/17)
〈その他〉
ジェームズ・ロバートソン超短篇「ある夜、図書館で」手書き拙訳稿の入ったトートバッグ をignition galleryで販売中。
バリー・ユアグロー超短篇「旅のなごり」手書き拙訳稿を包装紙にしたサンドイッチを、三軒茶屋のカフェnicolasで販売中。

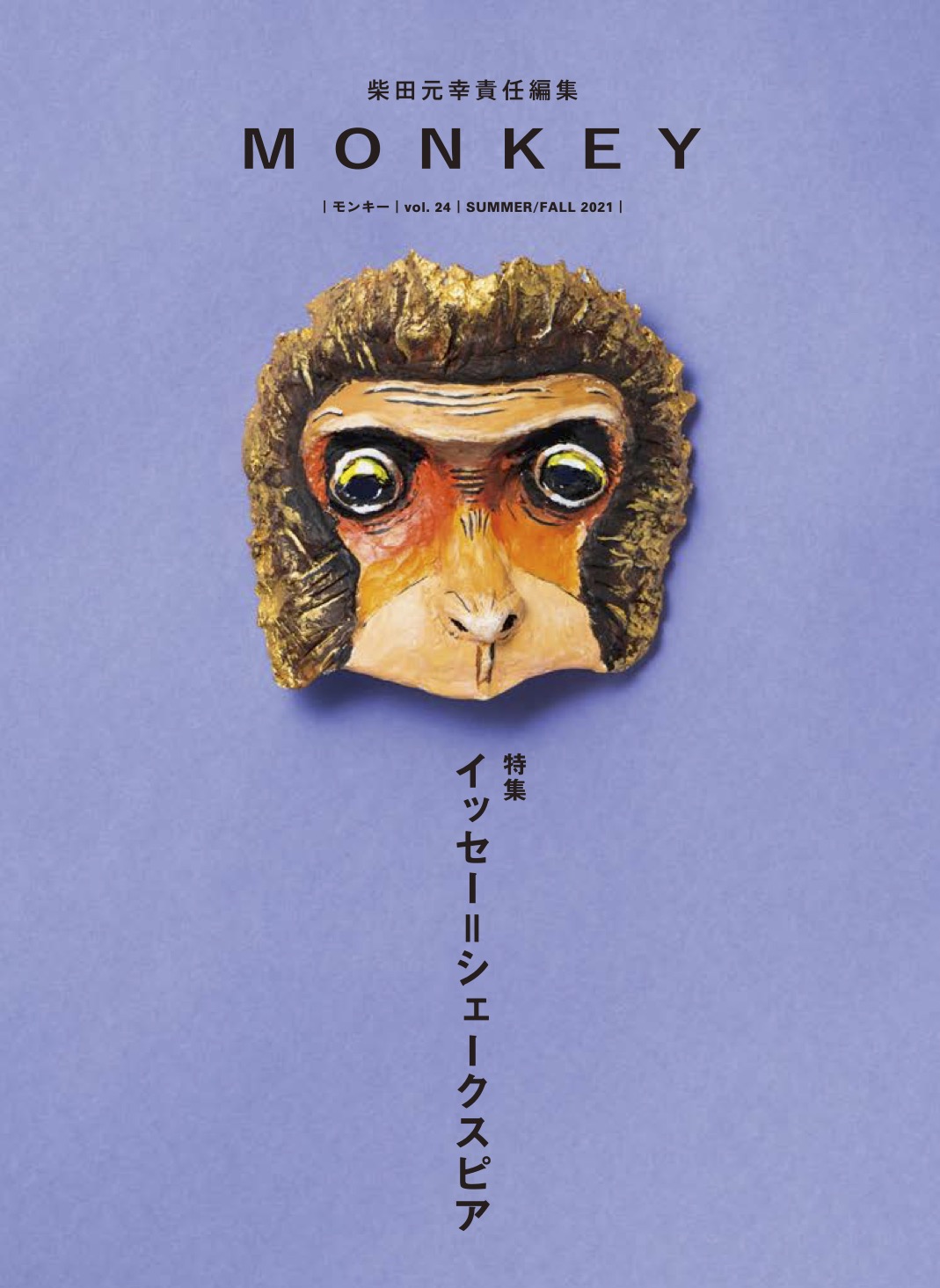





















Eley Williams, The Liar’s Dictionary (William Heinemann, 2020; paperback Windmill, 2021)