
毎月、猿が仲間に「ここにバナナがあるぞー」と知らせるみたいな感じに、英語で書かれた本について書きます。新刊には限定せず、とにかくまだ翻訳のない、面白い本を紹介できればと。
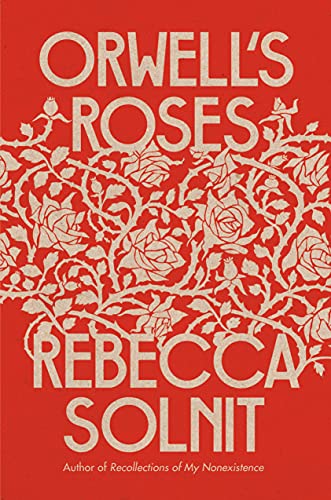
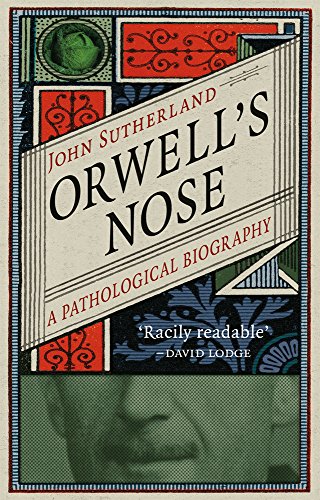
In the spring of 1936, a writer planted roses.(1936年の春、一人の作家がバラを植えた)
——レベッカ・ソルニットの新著Orwell’s Roses(『オーウェルのバラ』)はこの一文から始まる。
そう、売れない作家だったジョージ・オーウェル(当時32歳)は、イングランド南東部の小さな村に借りたコテージの庭にバラを植えた。ウールワース(日本でいえば西友あたり)で6ペンスで買った、何の変哲もないバラの苗木を。『1984年』『動物農場』といった小説や、「象を撃つ」などのエッセイを通して、人間の自由を押しつぶす組織の非人間性を鋭く描いた作家の、意外な趣味……と、たいていの人は思うだろうが、レベッカ・ソルニットはそこに、人間オーウェルの大事な核を見出そうとする。
Orwell often weighed in as a defender of roses, sometimes literally. In Tribune in January 1944 he wrote, “A correspondent reproaches me with being ‘negative’ and ‘always attacking things.’ The fact is that we live in a time when causes for rejoicing are not numerous. But I like praising things, when there is anything to praise, and I would like here to write a few lines—they have to be retrospective, unfortunately—in praise of the Woolworth’s Rose.” And then he celebrated the ones he’d planted in 1936. He was writing as the Second World War was raging around him. A few months later, as the Royal Air Force stepped up its bombing campaigns over Germany, he noted, “Last time I mentioned flowers in this column an indignant lady wrote in to say that flowers are bourgeois.”
オーウェル本人こそ、戦時中に花のことを書く人間を冷ややかな目で見そうなイメージかもしれないがそうではない、とソルニットは言う。オーウェルの作品を虚心に読めば、実は花をはじめ自然が与えてくれる喜びの記述に満ちていることを彼女は指摘する。そういう目で見れば、灰色が基調と思えていたオーウェルの文章に、色が見えてくる。そういう箇所は、いかにもオーウェルらしい鋭い政治分析を行なう際の切れ味はないかもしれないが、決して政治と無関係ではなく、“they have their own poetics, their own power, and their own politics. Nature itself is immensely political, in how we imagine, interact with, and impact it”(そこには独自の詩性があり、それ自身の力、それ自身の政治性がある。人間が自然を想像し、自然と相互に作用しあい、自然に影響を及ぼすなかで、自然それ自体がすぐれて政治的なのだ)。
とはいえこの本、オーウェルがそういう面も持っている人間だった、ということを証明するのが(少なくともそれだけが)目的なのではない。その点だけにとどまりつづけるには、バラが体現するものに対するソルニットの関心はあまりに広い。
かくして、オーウェルとは直接関係なく、写真家ティナ・モディッティが1924年に撮ったバラの写真の強烈なインパクトを語った章が挿入されたり、オーウェルと同じようにスターリンも庭を愛したことが述べられたり。第3部は“In the year 1924, a woman photographed roses.”という一文とともに始まり、第4部は“In the year 1946, a dictator planted lemons, or rather ordered them planted.”(1946年、一人の独裁者がレモンを植えた——というか、植えるよう命令を発した)とともに始まるのである。
とりわけ強い印象を残すのは、コロンビアで労働者を搾取してバラを大量生産し、北米のスーパーマーケットに安価なバラを供給している——その過程で環境も破壊している——システムについて語ったセクション‘The Ugliness of Roses’(バラの醜さ)である。ノーナンセンスなルポルタージュの手腕が発揮された、こういう章もあるのを見ると、ソルニットが現代のオーウェルのように見えてくる。
✴︎
さて、Orwell’s Rosesという本を読んだら、Orwell’s Noseという本も読まないわけには行くまい。こちらは少し前、2016年に出た。著者は英文学研究の大御所ジョン・サザーランド。
ソルニットはバラに対するオーウェルの愛着に目を向けたが、サザーランドは反対に、体臭、糞尿、腐敗等々にオーウェルが強く反応する人間だったことに目を向ける。これはもちろん有効な視点だと思うが、人間オーウェルを語るサザーランドの視点にはあまり共感できなかった。奨学生として名門イートン校に行ったオーウェルが、金持ちの同級生たちに対して屈折した感情を抱きながらも、卒業後、金に困ったときにはそれら金持ち同級生にずいぶん助けてもらったのに、小説では彼ら(と思しき人物たち)をずいぶん辛辣に描いたことをサザーランドはくり返し言い立てる。サザーランド自身が金持ち同級生の視点に立っているとは言わないが、そのように書いてしまうオーウェルの中に入ろうとするというよりは、そんなオーウェルを外から眺めて、ある種の病理をそこに見ているという印象が拭えなかった(サブタイトルのA Pathological Studyは「病理学的考察」)。
2冊を読んでから何かとバタバタしていて、あっという間に2か月以上が経ってしまった。ぼやぼやしていたら、今月刊行の『群像』(3月号)は何とレベッカ・ソルニット特集。管啓次郎、東辻賢治郎、ハーン小路恭子の3氏が充実した論考を寄せていて、管さんはOrwell’s Rosesにも言及している。こちらもぜひご覧下さい。
これからはまた月1回のペースで未訳作品を紹介するつもりです。どうかおつき合いくださいますよう。
最新情報
〈刊行〉
MONKEY26号「翻訳教室」2月15日刊行。
ポール・オースター文、タダジュン絵、柴田訳『オーギー・レンのクリスマス・ストーリー』(スイッチ・パブリッシング)発売中。
マシュー・シャープ、柴田訳『戦時の愛』(スイッチ・パブリッシング)発売中。
マグナス・ミルズ、柴田訳『鑑識レコード倶楽部』(アルテスパブリッシング)3月下旬刊行予定。
〈イベント〉(すべてオンライン)
2月11日(金・祭)午後2時00分~3時00分、朝日新聞記者サロン「翻訳家の柴田元幸さんが語る新訳『ガリバー旅行記』」。
詳細はこちら。
2月19日(土)午後2時00分~3時00分、MONKEY定期購読者限定オンラインイベント 平松麻・宮古美智代と。
2月22日(火)午後8時00分~9時30分、柴田元幸さんと祝う猫の日&エドワード・ゴーリーお誕生日会。
詳細はこちら。
2月23日(水・祭)午後2時00分~3時30分、MONKEY vol. 26刊行記念 柴田元幸+小島敬太 トーク&朗読会 。
詳細はこちら。
3月5日(土)午後3時30分~5時00分、朝日カルチャーセンター新宿教室「翻訳教室 90分一本勝負」(聴講のみ)。
詳細はこちら。
〈配信〉
コロナ時代の銀河 朗読劇「銀河鉄道の夜」 河合宏樹・古川日出男・管啓次郎・小島ケイタニーラブ・北村恵・柴田
《新日本フィル》朗読と音楽 ダイベック「ヴィヴァルディ」 朗読:柴田 演奏:深谷まり&ビルマン聡平
ハラペーニョ「謎」朗読音楽映像 ウォルター・デ・ラ・メア「謎」/ハラペーニョ=朝岡英輔・伊藤豊・きたしまたくや・小島ケイタニーラブ・柴田
〈その他〉
ジェームズ・ロバートソン超短篇「ある夜、図書館で」柴田手書き訳稿の入ったトートバッグ をignition galleryで販売中。
バリー・ユアグロー超短篇「旅のなごり」柴田手書き訳稿を包装紙にしたサンドイッチを、三軒茶屋のカフェnicolasで販売中。























John Sutherland, Orwell’s Nose: A Pathological Biography (Reaktion Books, 2016)