第1章 鶏カゴの女の子

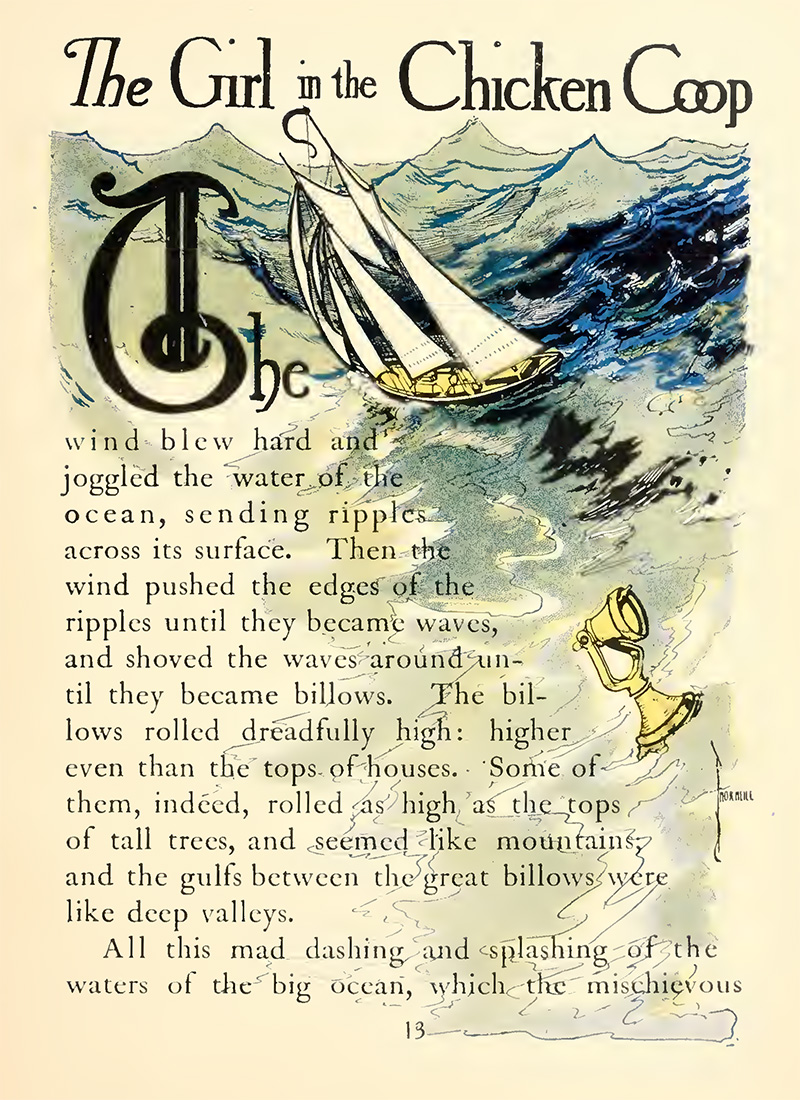 風が激しく吹きあれて、海を揺さぶり、水面にさざ波を立てた。さざ波の縁が風に押されて本物の波となり、なおも風に小突かれて大波となった。大波はすさまじい高さでうねり、家々の屋根よりもっと高くなった。なかには高い木のてっぺんまで達して、山みたいに見える波もあった。大波の合い間の淵は、深い谷のようだった。
風が激しく吹きあれて、海を揺さぶり、水面にさざ波を立てた。さざ波の縁が風に押されて本物の波となり、なおも風に小突かれて大波となった。大波はすさまじい高さでうねり、家々の屋根よりもっと高くなった。なかには高い木のてっぺんまで達して、山みたいに見える波もあった。大波の合い間の淵は、深い谷のようだった。
風がわけもなくこんないたずらをやったせいで、大海原はザブン、バシャンと狂おしく荒れ、じきに恐ろしい嵐となった。そして海の上の嵐というのは、やたらと妙な悪ふざけをやって、大きな害を為すものである。
風が吹きはじめたとき、一隻の船がはるか沖に出ていた。波が揺れ、転げ、どんどん大きくなっていくと、船は上下にのたうち、左へ右へ傾き、激しく揺られるあまり、船乗りたちですら、ロープや手すりにつかまらないと、風に飛ばされ海へまっさかさまに落ちてしまいそうだった。
空では雲が厚くたれこめ、陽の光も通らず、昼なのに夜みたいに暗く、嵐の恐ろしさはますます募っていった。
この船の船長は、いままでさんざん嵐を見てきて、そのたびに無事に船を操っていたから、この嵐も怖くはなかった。けれど乗客が甲板にぐずぐず残ったりしたら危険だとわかっていたから、全員キャビンに入らせて、嵐が過ぎるまで中にいるよう命じ、気を強くお持ちなさい、怖がることはありません、何も心配は要りませんからと伝えた。
さて、その乗客のなかに、ドロシー・ゲールというカンザスから来た女の子がいて、ヘンリーおじさんと一緒に、会ったこともない親戚を訪ねにオーストラリアへ向かっていた。ヘンリーおじさんはカンザスの農場であんまり働きすぎたせいで健康を害していて、体は弱り心も落ちつかなかった。それで、雇い人たちを取りしきり農場を守る役はエムおばさんに任せて、はるかオーストラリアに住むいとこたちを訪ねてゆっくり休もうと、こうして旅に出たのだった。
あたしも一緒に行きたい、とドロシーにせがまれ、ドロシーが一緒なら気も晴れるとおじさんも思ったので連れていくことにした。ドロシーはずいぶん旅慣れている。何しろカンザスからはるばるすばらしいオズの国まで大竜巻に運ばれて、あのふしぎな地でいろんな冒険をした末に、どうにかカンザスに帰ってきたのだ。だからちょっとやそっとじゃ怖気づかないし、風がヒューヒュー吠えだして波が激しく揺れはじめたときも、顔色ひとつ変えなかった。
「 そりゃもちろん、キャビンから出ちゃだめよ」とドロシーは、ヘンリーおじさんやほかの乗客たちに言った。「嵐が過ぎるまで、なるたけおとなしくしているのよ。甲板に出たら海へ吹きとばされちゃうって、船長さんが言ってるもの」
むろん、そんな危険をおかしたがる人はいない。乗客たちはみんな暗いキャビンで身を寄せあい、嵐の上げる金切り声、マストやロープがぎいぎいきしむ音を聞きながら、船が横に傾いたときもたがいにぶつからないよう努めた。
ドロシーはうとうと眠りかけたが、ハッと気がつくとヘンリーおじさんの姿が見えなかった。どこへ行ったのか見当もつかないし、おじさんはあまり丈夫でないのでドロシーは心配になってきた。ひょっとして、吞気に甲板に上がったりしたんじゃないか。だとしたら、すぐ下りてこないとおじさんの身が危ない。
実はヘンリーおじさんは、横になろうと自分用の寝台へ下りていったのだったが、ドロシーにはそんなことはわからない。覚えているのはとにかく、ちゃんとおじさんの面倒を見るのよ、そうエムおばさんから言われたということだけ。そこでドロシーは、嵐はますますひどくなっていたし海はもうほんとうに恐ろしい勢いで上下に揺れていたけれど、おじさんを探しに甲板へ行くことにした。でも甲板までの階段を上がるだけでも大仕事で、なんとか甲板に出てみると、風がものすごい激しさで叩きつけてきて、危うくスカートを飛ばされてしまいそうになった。けれどドロシーは、そうやって嵐に挑むことがなんだかうれしくて、胸がワクワクしてきた。手すりにしっかりつかまって、薄闇のなかでまわりに目を凝らしてみると、そんなに遠くないマストに、男の人が一人しがみついている姿がぼんやり見えた気がした。ひょっとしたらおじさんかもしれない。ドロシーは精いっぱいの大声で呼びかけた ——
「 ヘンリーおじさん! ヘンリーおじさん!」

けれど風がけたたましく叫び、吠えるものだから、ドロシーには自分の声もろくに聞こえず、とうぜん男の人にも聞こえていなかった。男の人はぜんぜん動かなかった。
こっちから行くしかない、とドロシーは覚悟を決めて、嵐が一瞬凪いだすきに前方に飛び出し、大きな四角い鶏カゴがロープで甲板に縛りつけてあるところをめざした。無事そこまでたどり着いたものの、鶏たちが入っている大きな箱の横板をドロシーがつかむや、こんな小さな女の子が挑んできたことに風が腹を立てたか、いきなり風の強さが倍になった。風は怒れる巨人のような金切り声を上げ、カゴを押さえつけているロープをもぎ取り、ドロシーが横板にしがみついたままのカゴを宙に持ち上げた。カゴはグルグル前後左右に旋回し、しばらくするとはるか下の海に落ちて、大きな波にとらえられ、波の斜面を押し上げられて泡立つ頂に達し、それから今度は深い谷間に急降下して、と、まるっきり波のおもちゃみたいにもてあそばれた。
ドロシーはもちろんどっぷり海中に沈んだが、一瞬たりとも落ちつきを失わず、がんじょうな横板から決して手を放さなかった。目から水を払ったとたん、風でカゴのふたがもぎ取られたことが目に入った。パタパタ羽を振る鶏たちはあっちへこっちへ風に飛ばされ、まるで把手のない羽根ぼうきみたいに見えた。カゴの底は厚い板でできていたので、なんだか横板付きのいかだにしがみついてるみたいだとドロシーは思った。これなら楽にあたしの重みに耐えるだろう。喉から水を吐き出し、また息ができるようになると、ドロシーは横板を這って越え、硬い木の底に降り立った。底板はドロシーの体をやすやすと支えてくれた。
「 これってあたし専用の船みたい!」とドロシーは思い、とつぜん変わった状況に怯えるどころか面白がった。やがて、カゴが大きな波のてっぺんまで上がっていくなか、元の船はどこかとドロシーは懸命にあたりを見まわした。
見れば船はもうずっと、ずっと遠くにあった。たぶんドロシーがいなくなったことにまだ誰も気づいていないだろうし、この奇妙な冒険のことも誰ひとり知らないだろう。波の合い間の谷にカゴはドロシーを乗せたまま降下し、ふたたび波のてっぺんに上がってくると、船はいまやずうっと遠くにいておもちゃのボートみたいに見えた。まもなく船は薄闇のかなたにすっかり姿を消し、ドロシーはヘンリーおじさんと離ればなれになってしまったことを嘆いてため息をついた。次はどうなるんだろう、とドロシーは思案した。
いまやドロシーは大海原の水面で揺られ、厚板が底にあって横板が付いたちっぽけな木の鶏カゴでかろうじて浮いている有様。横板のすきまから水がバシャバシャひっきりなしに飛びこんできて、ドロシーはもうすっかりびしょ濡れ! それにお腹がすいても食べるものは何もないし、きっとまもなくすいてくるだろう。飲み水もなければ、乾いた服もない。

「 まいったなあ!」とドロシーは笑いながら声を上げた。「あんたほんとに困ったことになってるわよ、ドロシー・ゲール! あんたがどうやってこれを切り抜けるのか、あたしには見当もつかない!」
厄介をさらに上のせするかのように夜が迫ってきて、頭上の灰色の雲はインクみたいなまっ黒に変わった。けれど風は、さすがにもういたずらは気がすむまでやったのか、海を吹き荒らすのをやめて、何か違うものを吹き荒らそうと、そそくさとよそへ去っていった。かくして、もはや揺さぶられなくなった波はおとなしくなり、まっとうなふるまいに戻っていった。
嵐がやんだのはドロシーにとって幸いだったと思う。やまなかったら、いくら勇敢とはいえ、さすがのドロシーも助からなかったかもしれない。こんな立場に置かれたら、しくしく泣いてすっかり絶望してしまう子どもも大勢いるだろう。でもドロシーはいままでさんざん冒険に出会って無事くぐり抜けてきたから、今回も取りたてて怖いとは思わなかった。まあたしかに体は濡れて心地よくはないけど、さっき言ったため息をひとつだけついたあとはもう、いつもの陽気さをそれなりに取り戻し、ここはひとつ、我慢づよく運命を待とうと決めたのだった。
やがて黒雲が去って頭上に晴れた夜空が見え、そのまんなかに銀色の月が優しく輝き、ドロシーが顔を上げると小さな星たちは明るくウィンクを送ってよこした。鶏カゴはもはや大揺れもせず、ほとんど揺りカゴみたいに穏やかに波に乗り、ドロシーが立っている床にももう横板のすきまから水が入ってきたりはしなかった。それを見て、また、この数時間の冒険ですっかり疲れたこともあって、ここは眠って力を取りもどすのが一番だ、それが一番楽な時間の過ごし方だとドロシーは決めた。床は濡れていて、体もびしょびしょだったけれど、幸いここの気候は暖かで、ぜんぜん寒くは感じなかった。
というわけでドロシーは鶏カゴのすみっこに座って、横板に寄りかかり、親しげに光る星たちに会釈してから目を閉じ、30秒後にはもう眠っていた。

*『オズのオズマ』が無料で楽しめるお得なMONKEY定期購読はこちら。
次ページ:『オズのオズマ』第2章 黄色いめんどり





















