第2章 黄色いめんどり
奇妙な音が聞こえてドロシーは眠りからさめ、目を開くと夜はもう明けていて、晴れた空に太陽が明るく照っていた。ドロシーはカンザスに帰った夢を見ていて、いつもの納屋の前庭で仔牛やブタやニワトリに囲まれて遊んでいた。眠気をさまそうと目をこすると、はじめはほんとにカンザスにいる気がした。
「ククク、カダク、ククク、カダク!」
あ、また聞こえた—— この奇妙な音で目がさめたのだ。これってどう考えても、めんどりが鳴く声だ! けれど、しっかり開いた目に、鶏カゴの横板を通してまず見えたのは、もうすっかり静かになった海の青い波で、そのせいで思いは一気に、危ないこと大変なことつづきだった昨日の夜に戻っていった。それとともに、自分が嵐をさまよう宿なしで、剣吞で未知の海の上を漂う身だということも徐々に思い出された。
「ククク、カダァァーーク!」
「え、何?」ドロシーは叫んで、思わず立ち上がった。
「うん、たったいま卵を産んだんだよ」と、小さいが鋭くはっきりした声が答え、ドロシーがあたりを見回してみると、カゴの反対側の隅っこに、一羽の黄色いめんどりがうずくまっていた。
「あれれ! あなたも一晩じゅう、ここにいたの?」ドロシーは驚いて声をはり上げた。
「もちろんだとも」めんどりは答え、羽をばたつかせてあくびをした。「カゴが船から吹きとばされたんで、この隅っこに、かぎつめとくちばしとでしっかりしがみついたのさ。水のなかに落ちたらおぼれて一巻の終わりだからね。まあここでも危うくおぼれるところだったけどね、何せ水がたっぷり押しよせてきたから。こんなに濡れたの、生まれてはじめてだよ!」
「そうよね」ドロシーも言った。「しばらくのあいだすごい水だったものね。で、いまはもう快適?」
「そうでもないね。お日さまが出て、あんたの服と同じであたしの羽もいちおう乾いたし、朝の卵を産んですっきりもしたけど、あたしらこれからいったいどうなるのかねえ、こんなバカでかい池に浮かんで?」
「あたしも知りたいわ」ドロシーは言った。「だけど、ねえ、あなたいったいどうしてしゃべれるの? ニワトリってクックッ、コッコッって鳴くだけかと思ってた」
「ああ、それはね」黄色いめんどりは考えぶかげに答えた。「あたしはたしかに生まれてずっとクックッ、コッコッって鳴くだけで、思いだせるかぎり、けさになるまで一言もしゃべったことはなかった。けどあんたにさっき、え、何、って訊かれて、ここはまあ答えるのがいちばん自然なことだろうって気がしたんだよ。で、しゃべったら、そのままずっとしゃべってるみたいだよ、あんたやほかの人間たちがやってるみたいにね。なんか変だよねえ?」
「すごく」ドロシーは答えた。「もしここがオズの国だったら、そんなに妙でもないでしょうけど。あのおとぎの国にはしゃべれる動物がいっぱいいるから。でもここは海のただなかで、オズからずいぶん遠いわよね」
「あたしの文法、どう?」黄色いめんどりは心配そうに訊いた。「あんたから見て、あたし、きちんとしゃべってるかい?」
「ええ、初心者にしてはすごく上手よ」
「ああ、よかった」黄色いめんどりは言い、こっそりした口調でつづけた。「なぜって、しゃべるんならやっぱり、正しくしゃべるのが一番だからね。赤いおんどりによく言われたよ、あんたのクックッ、コッコッは完璧だよって。で、今度はしゃべるのもきちんとやってるとわかってホッとしたよ」
「あたし、おなかがすいてきた」ドロシーは言った。「朝ごはんの時間よね、なのに朝ごはんはない」
「あたしの卵、食べてもいいよ」黄色いめんどりは言った。「あたし、自分じゃ食べないから」
「卵、かえさなくていいの?」ドロシーはびっくりして訊いた。
「いいや、いいんだ、卵をかえすんだったら、どこか静かな場所に、心地いい巣があって、パン屋の一ダースの卵にすわってるんじゃないとね—— それって13個ってことだよ、めんどりにはえんぎのいい数なんだ。だからこの卵、あんたが食べてくれていい」
「えーでも、食べるんだったら火がとおってないと」ドロシーは声を上げた。「けどご親切にありがとう、お気持ちはうれしいです」
「いいえ、どういたしまして」めんどりは涼しい顔で答え、羽をつくろいはじめた。

ドロシーはしばしそこに立ち、広い海を見わたした。でも頭では、まだ卵のことを考えていた。そこでまもなく、
「かえす気もないのに、どうして産むの?」と訊いた。
「習慣なんだよ」黄色いめんどりは答えた。「毎朝、羽が抜けかけるとき以外は、かならず新鮮な卵を産むのがあたしの自慢なんだ。卵をちゃんと産まないことには、朝のコッコッをやる気にもならなくて、コッコッをやらないと気分がわるい」
「ふしぎねえ」ドロシーが考えこんで言った。「でもまあ、あたしはめんどりじゃないから、わからなくても仕方ないんでしょうね」
「そうともさ」
そうしてドロシーはまた黙った。黄色いめんどりがいっしょでそれなりに楽しいし、ちょっとなぐさめられもする。けれどやっぱり、大海原の上というのは、おそろしく心ぼそいのだ。
しばらくすると、めんどりは飛び上がり、鶏カゴのてっぺんにとまった。ドロシーはさっきからカゴの床に座りこんでいて、そうするとカゴのてっぺんは、ドロシーの頭よりちょっと上にある。
「おや、陸も近いよ!」黄色いめんどりが声をはり上げた。
「どこ? どこなの?」ドロシーも叫び、ワクワクして思わず飛び上がった。
「ほら、あっちの少し先」ある方角をあごで指しながらめんどりは答えた。「あっちへ向かって流されてるみたいだから、お昼前には陸に戻れるんじゃないかね」
「だといいなあ!」とドロシーは言って、ふっとため息をついた。何しろ、板のすきまからときどき海の水が流れこんできて、そのたびに脚全体が濡れてしまうのだ。
「そうだよねえ」めんどりも言った。「この世で何がみじめと言って、濡れためんどりほどみじめなものはないからね」
陸はぐんぐん近づいているらしく、刻一刻ますますはっきり見えてきて、海に浮かぶ鶏カゴのなかにいる小さな女の子の目にはすごく美しく見えた。水ぎわには白い砂と砂利の浜辺が広がり、その向こうに岩の丘がいくつか見えて、さらにその先は緑の木々が連なり、そこから先は森であることを示していた。けれど家は一軒も見えなかったし、この未知の土地に人が住んでいる気配は少しもなかった。
「何か食べるものが見つかるといいなあ」迫ってくるきれいな浜に見入りながらドロシーは言った。「朝ごはんの時間、もうとっくに過ぎたもの」
「あたしもちょいとお腹がすいたよ」黄色いめんどりが言った。
「卵を食べたら?」ドロシーが言った。「あなたはあたしと違って、火が通っていなくても平気でしょ」
「あんた、あたしが共食いのケダモノだと思うのかい?」めんどりは憤慨して叫んだ。「そんなふうに侮辱されるなんて、あたしがいったい何をやったってのかね?」
「ごめんなさい、ミセス……ミセス……ところで、お名まえうかがってもいいでしょうか?」
「あたしの名まえはビル」いささかぶっきらぼうに黄色いめんどりは言った。
「ビル! それって男の子の名まえじゃない」
「それがどうしたっていうんだい?」
「だってあなた、ご婦人の鶏でしょ?」
「もちろん。だけど卵からかえったときは、めんどりになるかおんどりになるか誰にもわからなかったから、あたしが生まれた農場の男の子が、ビルって名まえをつけてペットにしたんだよ、かえったひなのなかで黄色いひよこはあたしだけだったからね。で、大きくなったら、あたしがおんどりみたいにコケコッコーって鳴いたりケンカしたりしないことはその子にもわかったけど、いまさら名まえを変える気もなかったから、納屋の前庭にいた動物みんなにも、家の人たちにも、あたしは『ビル』で通っていた。だからいままでずっとビルって呼ばれて、ビルがあたしの名まえなんだよ」
「だけどそれって間違ってるわ」ドロシーが真顔で言った。「もしよかったら、あたしあなたのこと『ビリーナ』って呼ぶわ。『ーナ』をおしまいに付けると、女の子の名まえになるのよ」
「うん、あたしはぜんぜんかまわないよ」黄色いめんどりは答えた。「あんたに何て呼ばれようといいよ、それがあたしのことだってはっきりしてさえいればね」
「わかったわ、ビリーナ。あたしの名まえはドロシー・ゲールよ、友だちにはドロシー、知らない人にはミス・ゲール。よかったらドロシーって呼んでちょうだい。いよいよ岸がすぐそばになったわね。あたしが水に入って、あそこまで歩いていくにはまだちょっと深すぎるかしら?」
「もうちょっと待つといい。日ざしはあたたかくて気持ちいいし、べつに急ぐことはないよ」
「でもあたしの脚、すっかり濡れちゃって」ドロシーは言った。「服はまあ乾いたけど、脚も乾かないとすっきりしないわ」
それでもめんどりに言われたとおり待つことにすると、まもなく大きな木の鶏カゴは、ギイッとおだやかに砂浜に流れつき、危険な航海は終わりを告げた。
言うまでもなく、難破した女の子とめんどりは、喜びいさんで陸に上がった。めんどりは飛び立ってたちまち砂に上がったけれど、ドロシーはまずカゴから這い出ないといけない。といっても、田舎に住む女の子にとってはべつに大したことじゃなかった。ぶじ陸に上がるや、濡れた靴と靴下を脱ぎ、陽であたたまった浜に並べて干した。
そうしてドロシーはすわり込み、ビリーナがやっていることを眺めた。鋭いくちばしで砂と砂利をつっつき、たくましいかぎつめで引っかいては引っくり返している。
「何やってるの?」ドロシーは訊いた。
「朝ごはんを調達してるのさ、決まってるだろ」忙しなくつっつきながらめんどりはもごもご言った。

「何があるの?」興味津々ドロシーは訊いた。
「そうだねえ、太った赤アリと、スナホリガニと、あとときどきふつうの小さいカニ。どれもすごく甘くておいしいんだよ」
「えー、気持ちわるい!」ドロシーはギョッとして叫んだ。
「何が気持ちわるいんだね?」めんどりは頭を上げて、明るい片目で旅の連れを見つめた。
「だって、生き物食べるんでしょ、それもゾッとする虫とか、ぞろぞろ這うアリとか。あなた、恥ずかしくないの?」
「何とまあ!」戸惑った口調でめんどりが言い返した。「ドロシーったら、おかしなこと言うねえ! 生き物の方が、死んでるのよりずっと新鮮で衛生的なんだよ。なのにあんたたち人間ときたら、ありとあらゆる死んだもの食べて」
「そんなことない!」ドロシーは言った。
「そんなことあるよ」ビリーナは答えた。「あんたらは仔ヒツジ食べて親ヒツジ食べて、ウシ食べてブタ食べて、おまけに鶏まで食べる」
「だけど火を通すもの」ドロシーは勝ちほこって言った。
「それで何がちがうのかね?」
「すごくちがうわ」ドロシーの声が重々しくなった。「うまく説明できないけど、とにかくちがうのよ。それにとにかく、人間は虫なんていう気持ちわるいものは食べない」
「だけど虫を食べる鶏は食べるだろ」黄色いめんどりは反論し、妙な声でクックッと鳴いた。「だからあんたらも、あたしたち鶏とどっこいどっこいだよ」
こう言われてドロシーは考えこんだ。たしかにビリーナの言うとおりだ。なんだか朝ごはんの食欲もなくなってきた。いっぽうビリーナは、あいかわらず砂をせわしなくつっつき、その食事ですっかり満足しているみたいだった。
やがて、水ぎわまで下っていたビリーナが、くちばしを砂の深くに突き刺したと思ったら、さっと引っこめてぶるっと震えた。
「痛っ!」ビリーナは叫んだ。「金属に当たっちまった、危うくくちばしが欠けるとこだったよ!」
「たぶん石ころじゃないかしら」ドロシーはろくに考えもせずに言った。
「何言ってるんだい。金属と石ころくらい区別がつくよ。触った感じがちがうんだ」
「だけどこんな人里はなれた海辺に、金属なんかあるわけないもの」ドロシーはなおも言った。「どこなの? あたしが掘ってみる。きっとあたしの言うとおりだから」
自分が「くちばしをぶつけた」と称する場所をビリーナが示し、ドロシーがせっせと掘ってみると、やがて硬いものに行きあたった。手をつっ込んで引っぱり出すと、それは大型の金の鍵だった——相当古いが、まだ艶はあるし、形も全然そこなわれていない。
「ほら、言ったとおりだろ?」めんどりは叫んで、得意げにクックッと鳴いた。「あたしが金属と言ったら金属かね、それともそいつは石ころかね?」
「たしかに金属だわ」ドロシーは答え、奇妙な掘り出しものをしげしげと眺めた。「これって純金だと思う。ずいぶん長いこと砂に埋もれていたにちがいないわ。ねえビリーナ、これどうやってここに行きついたんだと思う? このナゾの鍵、何を開けるんだと思う?」
「わかんないねえ」めんどりは答えた。「鍵だの錠だのは、あんたの方がくわしいはずだよ」
ドロシーは周りを見わたした。あたりには一軒の家の気配もない。でもどんな鍵だってそれが収まる錠があるはずだし、どんな錠にも何か目的があるはずだ、そうドロシーは考えた。ひょっとしてこの鍵、遠くに住んでいた人がこの岸辺に流れついてなくしたのかな。
そんなことをつらつら考えながら、ドロシーはワンピースのポケットに鍵をしまい、それから、もう陽にあたってすっかり乾いた靴下と靴をゆっくりはいた。
「ねえビリーナ、あたしこのへんちょっと回って、朝ごはんがないか見てみる」ドロシーは言った。
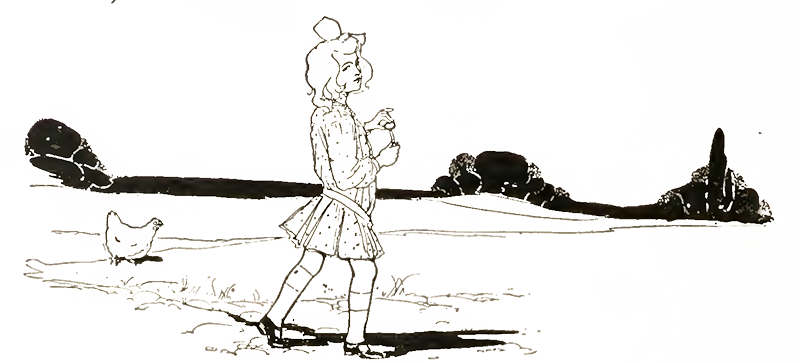
つづきが気になる方は、ぜひお得な定期購読をご検討ください!
文芸誌「MONKEY」を毎号あなたのお手元にお届けします。ご自宅はもちろん、オフィスやショップに毎号発売日(2月15日、6月15日、10月15日)までにお届けしますので、買い逃す心配もなく安心です。送料も無料!
通常価格(1320円×6冊):
→価格:6,000円 (うち税 545円)<24%OFF>
通常価格(1320円×3冊):
→価格:3,100円 (うち税 282円)<21%OFF>





















