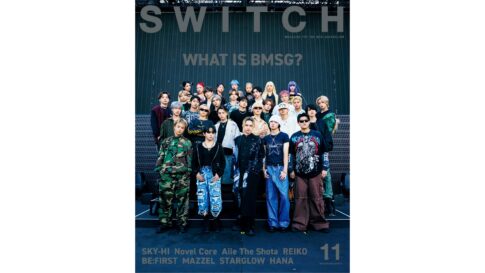多田玲子さんとは20年来の友達で、その間、お互い、ふんづまったり、気持ちがクサクサしていた時などは、励ましあっていました。多田さんの旦那さんで、絵描きの下平晃道さんと3人、お互いを褒め合いながら酒を飲む会などということもやっていました。3人はまだ、「自分はこんなことやっていていいのだろうか?」「これでやっていけるのだろうか?」と悩んでいました。しかし、そのような不安は、3人で話していると吹っ飛んで、「とにかくやってやるぞ」という気になれたのです。
そんなある日、多田さんに、「戌井さんは文章を書くといいよ」と言われ、さらに「そしたら、わたしが絵を描くよ」と言ってくれたのです。はっきりと覚えてないのですが、たしか酔っ払って乗ったタクシーの中で話したような気がします。どうだっけ? それから、半年くらい文章のやりとりをして、「ただいま おかえりなさい」という本を自主制作で作りました。この本は後に出版社から発売されることになるのですが、現在は絶版になってます。どなたか再版よろしくおねがいします。
多田さんとの出会いから、一緒に本を出すまでを、ものすごく簡単に説明しましたが、実は、このような説明や、わたしのことなどどうでも良いのです。
それよりも多田さんという人間、そのユニークさを皆に知ってほしいのです。まず多田さんと話していると頭の回転の早さに驚愕します。そのトークは、軽妙洒脱、含蓄があり、駄洒落があり、頓智もあり、早口言葉もあります。例えるなら、新橋で酔っ払っている駄洒落が得意なおじさんの、酔いを覚まさせ、頭の回転を七百倍にした感じです。
このように書いてると、お喋りすることが、多田さんの仕事みたいになってしまいますが、多田玲子さんはレッキとした絵描きで、イラストレーター、多方面で仕事をしています。その絵は、可愛く、毒があって、皆様もどこかで見たことがあるはず。例えるなら、新橋で酔っ払っている絵の上手いおじさんが、箸袋にチロチロ描いていた絵の900倍くらい素敵な絵を描きます。
なんだかよくわからなくなってしまいました。新橋と多田さんに親和性はありません。では、多田玲子さんのインタビューをどうぞ、場所は新橋ではなく青山です。
(戌井昭人・記)
「生まれたのは」
「生まれたのは福岡県の柳川市で、育ちは東京都の日野市、多摩川の分流、浅川の近くです」
「何歳まで柳川にいたの?」
「生まれただけ、親が柳川出身だったから」
「兄弟は?」
「お兄ちゃんがいます」
「じゃ日野市にすぐやってきて、そこでお育ちになったんですね」
「1回中野に住んで、幼稚園からは日野というより多摩川育ちです」
「遊びは、もっぱら多摩川?」
「当時、多摩川はすごい汚かったんだけど、川の中に入って、向こうの府中の方まで渡って帰ってきたりしてました。親にすごい怒られたけど」
「流されるかもしれないし、汚い」
「そうです」
「流されなかったからよかったけど、その頃の自分にまつわる事件とかありますか?」
「事件ね、うーん。脳みそが記憶を辿れないなー」
「じゃあ幼稚園に入っちゃいましょう。幼稚園はどうでしたか?」
「そうだな、いじめにあった。いわれのない理由で女の子の友達からいじめられて、こういうことがあるんだなってのを知りました」
「人間の嫌なところ?」
「はい」
「どんないじめにあったの?」
「でも考えるとそんなんでもなかったのかな。事件と言われて、いま頭のデーターベースを『チュンチュンチュン』って探ってるんだけど、『ジーコロコロ』って、遅い回線になっちゃってます」
「アクセスが悪くなってる」
「うん。なんかね、産前、産後で、記憶が、紀元前と紀元後みたいになってるの。だから産前の記憶がすごく曖昧になってるんです」
「お子さんは何歳だっけ?」
「8歳。でも思い出しますね。インタビューされると思って、いろいろ思い出しながら来たんだけど」
チュンチュンチュン、ジーコロコロ、アクセス!
「当時は、何をして遊んでた?」
「おままごととか、絵を描いてた。あとわたし、字を覚えるのが早かったんです」
「勉強してたの?」
「いや、親が漫画を与えてくれて、それで覚えたんです。幼稚園の時点で、スピリッツとか読んでました」
「おませというか、男子学生みたいだけど、他には、どんな漫画を?」
「『まことちゃん』」
「今日の服!」
多田さんが着ていたのは、白と赤のボーダでした。これは楳図かずお先生のトレードマーク。
「ありゃ! でもこれ偶然だし『まことちゃん』は、すごい好きってわけではなくて、『漂流教室』や『おろち』が好きだった。『まことちゃん』はお父さんが好きなんだ。他にお父さんは『どおくまん』が好きだった。でも『どおくまん』は読んじゃダメって言われてた。あとは、西岸良平の『三丁目の夕日』と、手塚治虫の『ブラック・ジャック』とか。お兄ちゃんも漫画が好きで『三丁目の夕日』のセリフを言い合ったりしてました。それは今でもやってるな」
「例えば、どんな風に?」
「突然は出てこないけど」
「お兄さんと喋ってると、勝手に出てきてしまう感じか」
「そうですね」

「当時は、漫画を描いたりはしてたの?」
「自分とお兄ちゃんが主役の漫画を描いてました。ホチキスでガチャンガチャン留めめて、九巻くらいになりました」
「どんな漫画だったの?」
「片山まさゆきって漫画家がいるんですけど、麻雀の漫画で『ぎゅわんぶらあ自己中心派』とか『スーパーヅガン』って、その漫画も家にあって、麻雀はよくわかってなかったんだけど、その人の絵を真似て描くのが好きで、その絵をコピーして、兄とわたしを描いてました」
「漫画の題名は?」
「題名は、『アダムとイブ』ですって、恥ずかしいんですけど」
「なんか禁断の兄妹みたいな、ヤバい話なの?」
「そういうんじゃない。なんにもわかってなかったんで、お兄ちゃんとわたしなのに」
「アダムとイブにしちゃったんだ」
「はい。恥ずかしいな」
「でも9巻て、すごいね。最後はどうなるの?」
「どうなったんだろう? なんだか恥ずかしいんで、思い出そうとするのを拒否してる自分がいます」
多田さん、ジーコロコロ、小学生へ。
「小学校は私立だったんですよね」
「桐朋学園で、国立まで通ってました」
「電車?」
「混みこみで大変だった。でも国立が良い場所で、あたりを歩くのが楽しかったな」
「どんな小学校生活でしたか」
「1年2年はおとなしくて、絵を描くのが好きで、髪の毛もモサーっとしてて、運動もあまりできなくて、けん玉してました」
「けん玉」
「なんだったんだろう。あんまり周りが見えてない小学生でした。髪の毛も前髪がモサーっとしてたから」
「髪で前が見えない」
「そうなの、いつも目の前に滝が『ザー』って流れてるみたいだった」
その滝は髪の毛だったけれど、意識的な滝でもあって、それが左右にひらかれるきっかけがあったそうです。
「幼稚園もいじめがあったけど、小学2年の時には、もっとキツい、いじめがあったんです」
「どんないじめだったの?」
「学校は2クラスしかなかったんだけど、同じクラスには帰り道が同じ方向の生徒がいなかったんです。だから1人で優雅に帰ってたんだけど、ある時、他のクラスの2人に、『一緒に帰ろうよ』と声をかけられて、それで帰るようになるんです。でも、その一人がすごい意地悪な子だった。最初は、わたし以外のもう1人の子がいじめられてたみたいなんだけど、それがわたしにまわってきて」
「理由なく」
「そう、いわれのないいじめ。でもいじめていた子は、気持ちがクサクサしてたんだと思う。お金持ちの家の子だったけど、親が、ちゃんとかまってくれてなかったとか」
「どんないじめだったの」
「教科書を破かれたり、制服のボタン取られたり、駅のトイレに閉じ込められて、モップでつっかえ棒されたり」
「本格的だな、小学2年なのに」
「そうなんです。そんなのがいろいろあって、でも、ある日、ハッと気づいたんです。『こんなことされてたらダメじゃん!』って、それまでは縮こまってたんだけど、もうこれは言わなくちゃって」
「それでどうしたの?」
「暴れました。『もう、こういうのやめ!』って。その子に向かって『先生にも言う。親にも言う、警察にも言う!』って、駅で暴れたんです。そしたら、向こうも子供だから『お願いだから言わないで』って言ってきた。でも、わたしは、『絶対に言う! じゃあ、失礼します』って帰ったんです。でね、その時のいじめで、制服のボタンを取られたんだけど、『ただいま』って家に帰ったら、『あらどうしたの?』って親に言われて、隣のクラスにこういう子がいて、これこれこういうことが色々あったんだって話したら、親が『なぬっ!』ってなりまして、学校に電話して、先生が集まって、親が集まって、会議が行われ、それで解決」
「よかった」
「そこからひらいたんですね」
「滝が」
「そう。こうなってちゃダメだ、言わなくちゃダメなんだと。それに体力もつきはじめて、髪も短く切って」
「髪の毛モサーっもひらけた」
「物理的にもひらけた。それで、次のクラス替えの時も、わたしは、いじめの主犯格の子とは一緒のクラスには絶対ならないように先生が配慮してくれて。平和な生活がはじまるんです。しかも三年生になったら、同じ帰り道の子供が転校してきて、シンガポールから帰ってきた子で、その子と親友になりました」
「その子と遊びながら帰ってたの?」
「ゲームセンターとか本屋に寄りながら帰った。あと、小学生なのに喫茶店に寄ってみたいと思ってた。でも普通の喫茶店は無理だから、ドトール寄ってみようかと、それでアメリカンコーヒーを飲むとかやってたな」
「小学生が」
「背伸びして」
「クラブ活動は?」
「5年生の時、まったく向いてないのに、バレーボール部に入りました」
「漫画の方は?」
「漫画は描きたかったし、描いてたんだけど、最後まで描く足腰がなかった」
「足腰?」
「始めても4ページくらいで終わっちゃう。最後までいかない」
「漫画以外は、どんなことを?」
「同居してたおばあちゃんが『TVガイド』を買ってて、終わった『TVガイド』をくれたんです。その映画の欄のあらすじを読むのが好きでした。それを切り取ってノートに貼ってました」
「なんだか、なんでもかんでも、どんどん吸収してく時期だったんですね」
「そう。それでいつかは漫画を描きたいと思ってるんだけど。いざやってみると描ききれない。でも一枚の絵を描くのは好きでした」
多田さんは、いまでも吸収する勢いが凄い。ちなみに『TVガイド』のスクラップはまだ家にあるそうです。では中学に入りましょう。