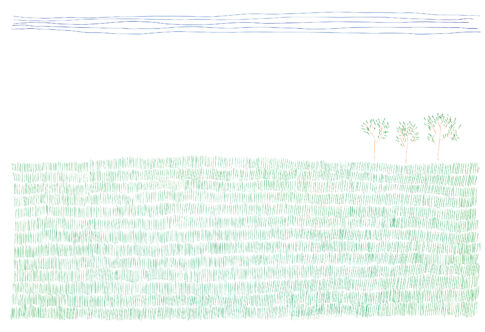文=戌井昭人
写真=浅田政志
ヘアメイク=白石義人
スタイリング=渡辺慎也
飄々としているのか、落ち着いているのか、そして、どこか謎めいた感じもする音尾さん。もちろんTEAM NACSの活動や役者としても知ってはいたけれど、いったいどんな方なのかと思っておりました。
これは、映画『孤狼の血』の影響によるものなのかもしれません。音尾さんは、ヤバいくらいに痛快な極道者を演じておりました。とにかく、この役の印象があまりにも強くて、ドキドキしながら、お会いすることになったのですが、会ってみると、ご本人は、とてつもなく穏やかで楽しい方でした。
ですから、その和やかな雰囲気に、音尾さんのキャッチコピーでもある『目と目の間は離れていても、アナタの心は離さない』という言葉が頭に浮かんできました。しかし、その目をよく見れば、たしかに離れてはいるけれども、奥底に、なんだかわからない底力をひしひし感じさせられるのでした。
北海道の地で、寒さと雪の中で遊びながら、ドジをしたり、とぼけたりしながら育った音尾さん。家族のエピソードも印象的で、底力のようなものは、育ってきた環境からにじみ出ているのかもしれないと思いました。(戌井昭人・記)
「お生まれは?」
「北海道の旭川市です。でも産まれてまもなく深川市に行って、小学生に入る頃、また旭川に」
「それは、お父さんのお仕事の関係で」
「そうです。ポリスマンだったので」
音尾さんは、映画『孤狼の血』で、ポリスとは、反対側の凄まじい役を演じていました。その存在感がもの凄かった。
「じゃあ、記憶があるのは深川からですね」
「深川で覚えているのは、家の裏にデカい工場があって、昭和ホーローってあったから、ホーローの工場だったんでしょうね」
「工場があるデカい街だった?」
「デカいというか、ギュッとした感じにつくられていました。子供の頃なので縮尺が今とは違って。デカいと思っていたけど」
「そこから旭川に引っ越して」
「はい。旭川は、小学校の入学式前に引っ越してきたので、友達が一切いなかったんです。ですから入学式の日は学校に行きたくないと言って、それでも母に連れられ、泣きながら歩いて行きました。それで、学校に着いてクラス分けされたんですけど、知ってる人がいないから教室に入れず。最初のホームルームには出ないで廊下にいました」
「先生が出席取ったらいなかった、と。音尾さんは『お』だから、出席番号は最初の方ですね。教室の窓際。その時教室に入れなかったのは、人見知りだったから?」
「そうです。幼稚園の時にも、おしっこに行きたいのを言えなくて、椅子の上でしちゃったことがあります」
「人見知りの音尾さんはどんなことをして遊んでました?」
「家の前に小さな川があって、どじょうを釣ったり、網ですくったり。たまにお祭りの金魚が泳いでました。それで、ある日突然鯉がその川に現れて、必死ですくって、家に持って帰ったら、母に『戻して来なさい』と怒られたのを覚えています」
「旭川だと、雪の思い出は?」
「とにかく雪は凄い。雪の日は田んぼがあったら、そこに飛び込んで泳いだりしてました」
「泳ぐ?」
「田んぼの中に2メートルくらい積もった雪の中に飛び込んで、ぐうぉーって、沈んで、そこを散々かき分けていくんです。そして汗だくになって帰る、と。あとは、どんなに雪に慣れていても毎年雪だるまは作ってました。あと、雪を丸めて、投げては、ぶつけ、壁にぶつけ、トラックにぶつけ。トラックにぶつけるとブウォンと跡がついて。これが定番の遊びでした。あとは、家の前に川があって、氷が張るんです。その上で遊んでました。5、6人で遊んでいると、どこかで、氷にバリッとヒビが入って、その時落ちるのは大概僕でした。で、泣きながら家に帰って風呂に入って。どんくさかったのかな。水泳はやっていたけれど、基本的に球技が苦手で。でも球技が苦手だったのは、早生まれのせいだったと思ってます。3月21日生まれで。最初は、周りが上手だから自分は下手に見えると思っていたけれど」
「お父さんがポリスマンだったら、柔道や剣道をやらされた?」
「それはなかったですけど、父が言うには、人間が死ぬ可能性があるのは水の中だから、水泳だけはやれ、と。それで水泳をやっていたんです」
「死なないために」
「陸地にいる限りは死なないけど、水の中は死ぬと。で、父はダイビングが好きで、30代の頃は警察を辞めてダイビングショップをやろうとしていたらしいです。でも、子供も2人目ができたし、しかも旭川、山の中なんですよ。山の中で、ダイビングショップやってもダメだろうと。それで諦めて、警察を続けたんです。だから水の中は大好きなんですね」
「一緒に連れていかれたりは」
「子供の頃は、車で3時間くらいかかる積丹半島に連れていかれて、キャンプをしていまして、物心ついた頃にはシュノーケリングをしてました」
「銛で魚を突いたり」
「そう。でも、うちの父は銛どころか、水中銃を持ってました」
「どんな魚を突いてたんですか」
「アイナメを獲って焼いて食べてました。ウェットスーツを着た親父が本格的に潜って。でも一番覚えているのは、ボンカレーです。キャンプではボンカレーというのが音尾家流でした」

「北海道は、キャンプのような遊びができるのは夏場だけですよね」
「そうです。でも海に入っても冷たいんです。で、ゴムボートで沖の磯にある、ローソク岩というところに行って、ゴムボートに母を乗せたまま、男たちは、潜ってました。その岩のところから一気に深くなって、20メートルくらいになるんですけど、父はガンガンに潜ってました。あと、山菜採りも行ってました」
「家族単位で動いていた」
「はい、家庭密着型の子供でした。あと母方の実家がお菓子工場を営んでいまして、祖母が言うには、昔は駅前から行列ができるくらい有名なせんべい屋だったと。でもその時は、どら焼きとかあんこ系のものを機械で作ってたんです、焼くのも機械、あんこ出すのも機械、最後にパートのおばさんたちが箱に詰めたり封をしたり。それで、そのお菓子の配達の車によく乗ってました」
「配達する人は」
「おじさんです。ぼくは、おじさん子でした。そのおじさんと、スーパーとか、パン屋とか温泉地に置かれる箱入りのお菓子を配達するのに付いていってました。おじさんは独身で、ぼくが欲しいという漫画をだいたい買ってくれました。『Dr.スランプ アラレちゃん』とか」
「おじさんといると、どんどん漫画が揃っていく」
「そうです。だからこそ、おじさん子だったんです。欲しいものを買ってくれる。一方で、父は厳しい人という感じがあった」
「ポリスマン」
「この前、おばさんに聞いたら、『一時期、あんたのお父さん、やっぱ目つき違ったもんね』と言われました。目つきがものすごかったと。そこまでは思い出せないんですけど、やっぱり、マル暴でしたから、本人がそっちなんじゃないかというレベルでした。威圧感もすごくて、逆らうとか一切できなかった。家にいたらすごい熱がある感じで」
「でも、海に行ったら魚を獲ってきてくれるし、頼もしい」
「そうです。遊ぶ時はよかったけど。子供の頃は、ご飯は正座で食べるのが決まりでした」
「キャンプやボンカレーのときは自由?」
「そう、自由になれるんですよ。だから、そっちは楽しい思い出ばかりなので、覚えているんです」
「お父さんが柔らかくなると」
「そうです」
「お父さん自身も、海に行くと解放されていたのかもしれませんね」
「海の中にヤクザはいなかったから」
中学生活はどうだったのでしょうか?
「部活は入ってましたか?」
「水泳をやろうか迷ったんですけど、水の中にいると死にそうだからやめました。それで最初は気楽そうな卓球部に入ったんですけど、2カ月で辞めて、あとは何もしませんでした」
「じゃあ、家に帰ってからはなにを?」
「ゲームです。ファミコンですね。うちは、小学6年生くらいになって、ようやく買ってもらえました。それで夜中、みんなが寝静まったら、起き出してやってました」
「じゃあ、そっちの冒険、ロールプレイングの冒険へ向かっていたんですね」
「そうです。あと、その頃ファミコンの『ディスクシステム』が出て」
「ディスクシステムありましたね、『ゼルダの伝説』」
「ディスクシステムは革新的でした」
「書き換えられる」
ここで、しばらく任天堂のディスクシステムの話で、盛り上がってしまいました。
「あとは、塾に通わされて、そこで、塾の友達ができました。下川くん、スケボーで、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』ごっことかして遊んでました」
「映画とか芝居とか、今に関わることは好きだったんですか?」
「いっさいなかったです。ジャッキー・チェンは観てましたけど」
「お兄さんの影響は?」
「兄は、アニメが好きだったんです。だからそれを見て、自分はアニメ好きになるのはやめようと思っていました」
「お父さんはアニメが好きだったり、ゲームばかりやっている子供達をどう思っていたのでしょうか?」
「とくになんだかんだ言われなかった。でも兄貴は柔道やってました」
「他に、中学時代の思い出は?」
「そんな悪いことをやってたわけではなかったですけど。クラスで一番強い奴がいて、そいつと話している時に、好きな女の子の話をしてたら、『じゃあ、オトちゃん告白しに行こうぜ』となったんです。なんだか、そうしなくちゃいけない流れになってしまい、休み時間に呼び出されて、告白する流れになりました。その女の子も、友達を連れて出てきました。でも『好きだ』と言えず」
「見物人がやたらいるんですよね」
「そうです。そうしたら次の日からクラスの様子がおかしくなって、話しかけても、なんかおかしいぞ、話してくれないぞ、と。もしかしたら、これはアレかと思って。で、中二なった時に、『オトちゃんいじめられてたんでしょ』『無視されてたんでしょ』って言われて、そこで真相がわかった」
「気づいているような、気づいていなかったような。帰宅部だったから」
「そうそう、それまで話していた奴とは話せず、話していなかった奴と話すようになってた。でも今思い返すと、自分の中では辛かったのかもしれません」
「告白できなかったくらいで無視って、周りもなんだかセコいですね」
「そうなんですよ。そのクラスで強い奴が『無視しよう』と言い出したらしいんです。でも中学2年の時に、やっぱりその女の子が好きだと思って」
「好きな気持ちは変わらなかった」
「はい。それで手紙をそっと、その女の子の家の玄関に置いてきたんです」
「やりましたね」
「でも、返事がない。それで、2週間くらいしたら、その子の友達から手紙を渡され、『付き合えないと言っています』とありました」
音尾琢真 1976年北海道旭川生まれ、演劇ユニットTEAM NACSメンバー。北海学園大学在学中に森崎博之と戸次重幸に誘われ、同期の大泉洋とともに演劇研究会に入部、これがTEAM NACS結成のきっかけとなる。最新出演作は2月公開の映画『七つの会議』(監督・福澤克雄)
戌井昭人 1971年東京生まれ。作家、パフォーマンス集団「鉄割アルバトロスケット」の旗揚げに参加、脚本を担当。『鮒のためいき』で小説家デビュー、2013年『すっぽん心中』で第四十回川端康成文学賞、16年『のろい男 俳優・亀岡拓次』で第三十八回野間文芸新人賞を受賞。最新刊は『ゼンマイ』